勤怠管理システム選びで知っておくべき比較ポイントをわかりやすく解説

勤怠管理システムは、従業員の勤怠状況を記録・自動集計し、人事労務管理を効率化するシステムです。
働き方改革の進展による勤務形態の多様化や労働時間管理の厳格化がみられるなか、紙やExcelを用いた勤怠管理と比べて対応時間を大幅に削減できるため、導入を検討する企業も多いでしょう。
しかし、勤怠管理システムにはさまざまな種類があり、「どれを選べばよいのか?」と悩む人事労務担当者も少なくありません。
そこで、本記事では勤怠管理システムのメリットや注意点を整理し、選び方のポイントなどをわかりやすく解説します。
自社に最適なシステムを見極め、人事労務管理の効率化を目指しましょう。
この記事の目次
勤怠管理システム導入のメリット6つ
勤怠管理システムを導入すると、人事労務管理の精度が向上し、業務の負担が軽減されます。
紙やExcelを用いた管理では手作業に頼る部分が多く、入力ミスや集計の負担が大きいという課題がありました。
また、働き方改革(※)の推進によって労働時間の厳格な管理やテレワーク対応が求められる中、従来の管理方法では対応が難しい場面も増えています。しかし、勤怠管理システムを活用すればリアルタイムでの労働時間の把握をはじめ、出退勤データの自動集計が可能になり、法令遵守の強化や労務リスクの低減にもつながります。
ここでは勤怠管理システムの導入時に押さえておきたい以下の6つのポイントについて、わかりやすく解説します。
※(参照)厚生労働省「働き方改革関連法に関するハンドブック」
①給与計算業務を効率化できる
勤怠データの自動集計により、給与計算に必要なデータの作成業務を効率化できるのは、勤怠管理システムの大きな利点です。
給与計算は、人事労務管理の中でも手間のかかる業務のひとつです。従業員の勤怠データを手作業で集計し、給与システムに入力する工程は、時間がかかるうえにミスのリスクも伴います。
しかし、勤怠管理システムを導入すれば、出勤・退勤データがリアルタイムで自動集計され、給与計算システムとスムーズに連携できます。それにより手入力の手間が削減され、データの正確性も向上します。
たとえば、残業時間や深夜手当の自動計算機能を活用することで、給与計算の負担をさらに軽減することができるでしょう。また、人為的な計算ミスの防止にもつながり、給与支払いのトラブルを回避できるのも大きなメリットといえます。
②打刻忘れや不正を防止できる
勤怠管理システムには打刻忘れを防ぐアラート機能や、生体認証などによる本人確認機能が搭載されており、不正打刻の防止に役立ちます。また、リモートワークや直行直帰の多い職場では、GPS機能付きの打刻システムを活用することで勤務状況の透明性を確保できます。
適正な人事労務管理には正確な勤怠記録が欠かせませんが、手作業による管理では打刻漏れや不正打刻が発生しやすく、正確な記録を維持するのが難しくなります。
しかし、勤怠管理システムを導入することでこうしたリスクを未然に防ぎ、信頼性の高い打刻データをもとにした人事労務管理が可能になります。
さらに、正確な打刻データをもとにした勤怠管理は、コンプライアンス強化や業務負担の軽減にもつながります。
③多様な働き方に対応できる
勤怠管理システムを導入すると、多様な働き方に対応しながら人事労務管理の負担を軽減できます。
近年、働き方の多様化により勤怠管理の複雑化が進み、紙やExcelなどによる管理方法では、異なる勤務形態への対応が難しい場面も増えてきました。
労働時間や休暇取得に対する確認作業の負担も増えるため、より効率的な勤怠管理の手法が求められています。
そうした中で勤怠管理システムを活用すれば、以下のような機能により柔軟な人事労務管理が可能となります。
- 勤務・雇用形態ごとの時間集計:正社員、契約社員、パート・アルバイトなど、多様な雇用形態に対応
- シフト管理の効率化:シフト作成や変更、共有がスムーズに行える
- リモートワークの打刻対応:場所を問わず正確な勤怠記録を保持
- 労働時間の可視化:長時間労働の防止や適正な勤務管理を支援
新たな働き方を取り入れたい企業や、従業員数が増加してきている企業では特に、勤怠管理システムの導入メリットを得られるでしょう。
④長時間労働を防げる
勤怠管理システムを導入すると、労働時間をリアルタイムで把握できるため、長時間労働の抑制や労働基準法に基づく36協定(時間外労働の上限規制)(※)の遵守がスムーズに行えます。
また、残業時間が一定の基準を超えるとアラートで警告を発する機能があるため、管理者も迅速に適切な労務管理が可能です。
こうして過重労働が防止され、働きやすさが向上すれば、従業員の健康維持にもつながります。
さらに、法令改正にも柔軟に対応でき、コンプライアンスの強化にも貢献します。結果として安心して働ける環境が整い、業務効率も高まってくることでしょう。
※(参考)「厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」
⑤有給休暇管理がスムーズに行える
勤怠管理システムは有給休暇の申請・承認をオンライン化し、取得状況を自動で集計できるため、スムーズな管理を実現します。
2019年の法改正により、企業には年5日以上の有給休暇取得が義務付けられました。(※)
しかし、手作業での管理では休暇の取得状況の把握が難しく、記録漏れが発生することもあり得ます。一方で勤怠管理システムを導入すれば、従業員自身がリアルタイムで残日数を確認できるようになります。
計画的な休暇取得が促進すれば、管理者も労務管理の負担が減り、従業員のワークライフバランス向上と法令遵守が両立します。
結果的に働きやすい環境が整い、企業全体の生産性向上にもつながっていくのではないでしょうか。
※(参照)厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
⑥法令違反を回避できる
残業時間が一定の基準を超えた際のアラート機能や、有給休暇の取得状況を自動で集計する仕組みによって適切に労務管理が行えるため、法令違反のリスクを未然に防ぐことができます。
また、システムの自動アップデートにより法改正にも迅速に対応でき、最新のルールに沿った運用が可能です。
企業には労働基準法をはじめとする法令を守り、適正な労務管理を行う責任があり、特に長時間労働の抑制や有給休暇の取得管理はコンプライアンスの観点からも重要です。
適切なシステムを導入することで管理の負担を軽減しながら、企業の評価向上にも貢献します。
勤怠管理システム選びの失敗例から学ぶ注意点
勤怠管理システムは、どの製品を選んでも必ず自社の業務効率化につながるというわけではありません。
自社の勤務形態や規模に適したシステムを選ばなければ、かえって管理の負担が増えることもあります。
たとえば必要な機能が不足していたり、運用コストを見落としていたりすると、導入後に活用しにくくなるケースがあるので注意が必要です。
ここではシステム導入の失敗例をもとに、選定時のポイントを解説していきます。
導入コスト(初期費用)がかかる
クラウド型のシステムは「月額料金のみで導入できる」と思われがちですが、実際には初期設定費用やカスタマイズ費用が発生する場合があります。
勤怠管理システムの導入に際し、運用コストにばかり注目してしまい、初期費用を見落とすケースは少なくありません。
また、既存システムとの連携やデータ移行に追加費用がかかることもあるため、トータルのコストを把握しておくことが重要です。
システムを比較検討する際は、運用コストだけでなく、導入時にかかる費用も事前に確認しておきましょう。
自社の勤怠ルールに合わないことがある
勤怠管理システムの導入後、「自社の勤怠ルールに対応していない」と気づくケースがあります。
企業ごとに勤務形態や就業ルールは異なり、フレックスタイム制や裁量労働制、パート・アルバイトなどに対応できるシステムを選ぶことが重要です。
たとえば、一部のシステムでは複雑なシフト管理や変則勤務に対応できず、手作業が残ることもあります。
システム導入前に自社の就業ルールに適合するかどうかは、事前に問い合わせるなどして、しっかり確認しておきましょう。
操作に慣れが必要な場合がある
システムの運用には慣れが必要なこともあり、導入時には操作性の確認が大切です。
特に従業員側に使いにくさが感じられると、定着がスムーズにいかなくなったり、人事労務担当の問い合わせ対応の手間が増えたりしてしまいます。
そこで導入前のトライアルサービスなどを活用し、実際の運用を試してみることをおすすめします。
また、シンプルで直感的に使えるシステムや、導入後のサポートが充実したものを選ぶことでスムーズな運用が可能になるでしょう。
適切な選定と準備を行うことで、勤怠管理効率化の効果を最大限に得られます。
勤怠管理システムの種類は大きく2つ
勤怠管理システムには、大きく分けてクラウド型とオンプレミス型の2種類があります。
- クラウド型:インターネット経由でシステムを利用する方式
- オンプレミス型:社内サーバーにシステムを構築して運用する方式
以下の表の通り、それぞれに特徴があり、企業の環境やニーズに応じた選択が求められます。
| 項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |
|---|---|---|
| 導入コスト | 比較的低い | 高い(サーバー購入と構築が必要) |
| 運用コスト | 低い(月額料金制) | 高い(自社で保守・管理費用が必要) |
| 導入スピード | 早い(申し込み後すぐ利用可能) | 遅い(サーバー構築・設定が必要) |
| カスタマイズ制 | 低~中(提供機能を利用) | 高い(自社仕様に併せて開発可能) |
| セキュリティ | 高い(システム提供会社が管理) | 高い(自社管理なので負担は大きい) |
| アップデート・法対応 | 自動で更新 | 自社で対応 |
| システム障害時の対応 | システム提供会社が対応 | 自社で対応 |
オンプレミス型は自社の運用に併せてシステムの構築や運用ができる反面、多くの時間と費用が必要です。
一方でクラウド型は、費用を比較的抑えながらスピーディに導入・運用開始でき、セキュリティやアップデートを自社で管理する必要がないため、現代の働き方に適している勤怠管理システムだといえます。
また、導入ハードルが高くないため、クラウド型の勤怠管理システムは多くの企業へおすすめです。
勤怠管理システムの選び方と比較ポイント7つ
勤怠管理システムの導入には、自社の業務に適したシステムを選ぶことが重要です。
必要な機能やコスト、運用のしやすさなど、複数の観点から比較することで失敗を防ぐことができます。
ここではシステム選定時に押さえるべき、以下の7つのポイントを解説します。
導入後に「想定と違った」とならないためにも、比較のポイントを確認しましょう。
<ポイント①>自社の勤怠ルールに必要な機能が備わっているか
企業ごとに勤怠ルールは異なるため、システム選定の際には搭載している機能が自社の勤務形態に対応できるかどうかを確認する必要があります。
たとえば、フレックスタイム制・裁量労働制・変形労働時間制・パート・アルバイトなど、多様な勤務形態に対応できるかといったようなことです。
また、休暇管理や残業申請、シフト作成など、自社の業務に不可欠な機能が備わっているかを事前にチェックしましょう。必要な機能が不足していると、導入後に手作業が残り、管理負担が軽減されない可能性があります。
システム選定時には実際の運用を想定しながら、必要な機能が揃っているか確認することが大切です。
<ポイント②>導入および運用コストは適正か
システム導入には初期費用や月額利用料が発生するため、そのコストが自社での運用に適正かどうかを事前にチェックしておきましょう。
特にクラウド型とオンプレミス型では費用の構造が異なるため、コスト面の確認が必要です。
また、導入後のメンテナンス費用やアップデート対応の有無も考慮し、トータルコストを見極めることが重要です。
単に初期費用の安さだけで判断せず、長期的な運用コストまで含めて検討しましょう。
<ポイント③>既存システムとの連携性はどうか
既存の給与システムや人事管理システムと連携できるかを確認することが重要です。
連携がスムーズでないと、データの二重入力や手作業の増加につながり、業務効率化が十分に図れない可能性があります。
たとえば、給与計算システムと連携できれば勤怠データが自動で反映され、給与計算の負担を軽減できます。また、シフト管理や経費精算システムと連携することで、業務全体の効率向上にもつながります。
「導入したものの手作業が増えてしまった」という事態を避けるためにも、システム間の相性をしっかり見極めておきましょう。
<ポイント④>管理者と従業員双方の使いやすさはどうか
システムを導入する際には、管理者(人事労務担当など)と従業員の双方が使いやすいかどうかをしっかりチェックしておきましょう。
管理者は勤怠データの集計や労働時間の管理をスムーズに行えるかがポイントとなり、従業員にとっては打刻や休暇申請のしやすさが業務負担の軽減につながります。
使いやすいシステムのチェックポイントの例は、具体的に以下の通りです。
- 直感的な操作性:シンプルな画面設計で、迷わず操作できる
- スマートフォン対応:外出先やリモートワークでも簡単に打刻・申請が可能
- カスタマイズ性:自社の勤怠ルールに合わせた設定変更が容易
- サポート体制の充実:問い合わせ対応やマニュアルが整備されている
システム選定時にはデモ体験やトライアルを活用し、実際の使い勝手を確認することが大切です。
<ポイント⑤>法令への対応は十分に配慮されているか
勤怠管理システムを選ぶ際には、最新の労働関連法に適合しているかを確認することが不可欠です。
特に、働き方改革関連法や時間外労働の上限規制など企業が遵守すべきルールが年々変化するため、システムが適切に対応しているかを見極める必要があります。
事前に確認すべき法令対応面における機能の例は、具体的に以下の通りです。
- 勤務時間の自動集計:勤務・雇用形態に応じた適正管理ができるか
- 休暇管理機能:年次有給休暇の取得義務に対応しているか
- 36協定に応じた設定:時間外労働の上限規制に関する管理が可能か
- 法改正への迅速な対応:アップデートや通知機能があるか
企業のコンプライアンスリスク(労務リスク)を最小限に抑えるためにも、法令対応がしっかりしたシステムを選びましょう。
<ポイント⑥>セキュリティやサポート体制は充実しているか
勤怠データには、従業員の個人情報や給与情報が含まれるため、強固なセキュリティ対策が求められます。
また、導入後のスムーズな運用のために、サポート体制の充実度も重要なポイントです。
セキュリティやサポート体制が充実しているのか、以下のポイントを参考に確認してみてください。
【セキュリティ対策】
- データの暗号化:通信・保存データが安全か
- アクセス管理機能:権限設定が柔軟にできるか
- ログ管理機能:不正アクセスの監視が可能か
- データセンターの安全性:国内外のサーバー管理体制が整っているか
【サポート体制のチェックポイント】
- 導入時のサポート:初期設定や運用相談が可能か
- 問い合わせ対応の充実度:電話・メール・チャット対応の有無
- トラブル時の対応スピード:障害発生時の対応フローが明確か
<ポイント⑦>導入前のトライアルサービスが用意されているか
勤怠管理システムの使い勝手や自社の業務フローに合致しているかを判断するためには、無料トライアルやデモ版の活用が有効です。
多くのシステム提供会社が一定期間の試用サービスを提供しているため、以下のポイントを参考にして、事前に実際の操作感を確認しましょう。
- 管理者画面の操作性:勤怠データの入力・編集が簡単か
- 従業員向けの使いやすさ:スマホアプリやPCでの打刻がスムーズか
- レポート機能の充実度:勤怠データの出力や分析がしやすいか
- 他システムとの連携:給与計算ソフトとのデータ連携が可能か
導入後に「思っていたものと違った」とならないよう、事前のトライアルを積極的に活用しましょう。
勤怠管理システムの選定ポイントに関してよくある質問
勤怠管理システムを導入する際、企業ごとにさまざまな疑問が生じます。
「どのシステムが自社に合うのか?」「コストはどれくらいかかるのか?」「運用後のサポートは?」など、選定前に知っておきたいポイントを解説します。
勤怠管理システムの選び方は中小企業と大企業で違う?
企業規模によって、勤怠管理システムに求められる機能やコスト感は異なってきます。
以下の比較表を参考に、自社に合ったシステムを選びましょう。
| 比較ポイント | 中小企業向け | 大企業向け |
|---|---|---|
| コスト | 低コストで導入しやすい | 大規模導入に適した価格帯 |
| 必要な機能 | 基本的な勤怠管理機能 | シフト管理・労務分析・多拠点対応 |
| 運用負担 | シンプルで扱いやすい | IT部門や人事部での管理が必要 |
| セキュリティ | 標準レベル | 高度なセキュリティ対策が必須 |
建設業の勤怠管理システムの選び方は?
建設業界は現場作業が多いため、勤怠管理システムにも業界ならではの働き方に合わせた機能が求められます。
建設業界向けのシステムの選定ポイントは次のようになります。
- モバイル打刻対応:GPS機能付きのアプリが便利
- シフト管理の柔軟性:日ごと・週ごとの勤務調整が可能
- 労働時間の適正管理:時間外労働の上限監視機能がある
- 給与計算との連携:現場ごとの給与計算がスムーズ
- 工数の管理:必要な作業量を算出できる
上記も参考にして、建設業界での実際の働き方をイメージしながら、対応する機能がある勤怠管理システムを選びましょう。
安価な勤怠管理システムの選定ポイントは?
導入コストを抑えることができればそれに越したことはありませんが、導入後に必要な機能を追加していった結果、「想定よりも高額になってしまった」などといったこともあり得るでしょう。
コストを抑えつつ長期的に使いやすいシステムを選ぶためには、単に「基本料金の安さ」だけでなく、初期設定や運用開始後のサポートの有無、必要な機能が充実しているかなど実際の運用状況を見据えたトータルコストを考慮することが大切です。
クラウド型勤怠管理システム「楽楽勤怠」で人事労務管理業務の課題を解消
「楽楽勤怠」は、企業ごとの運用ルールや法律に対応できるクラウド型勤怠管理システムです。
出退勤データの自動集計やシフト管理、残業・有給取得状況の可視化など、必要な機能が十分に備わっており、人事労務管理の負担を軽減します。
また、導入前の相談から運用開始後のサポートまで充実した体制を提供し、初めての導入でも安心です。
さらに「楽楽勤怠」は、働き方改革関連法などの法改正にもスピーディに対応しており、従業員の健康管理や働きやすい環境の整備にも貢献します。
勤怠管理システム導入の際は、ぜひ一度お問い合わせください。
メールで受け取る

働き方改革関連法へ対応!勤怠管理システム「楽楽勤怠」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
- 監修楽楽勤怠コラム編集部
- 「楽楽勤怠」コラム編集部です。
人事労務担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報をお届けしています。
https://www.rakurakukintai.jp/
こんなお悩みありませんか?
そのお悩み で解決できます!
で解決できます!

実際のシステム画面をお見せしながら
現在の運用方法についてお伺いし、
貴社に合わせた運用提案を
させていただきます。
ご要望に合わせてWEBでのご案内も可能です。
知りたい方はこちら

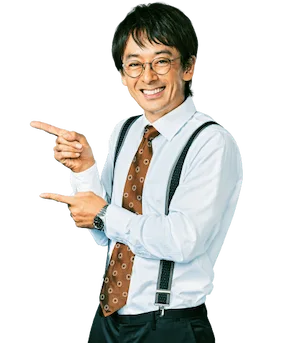
 とは
とは
「楽楽勤怠」は勤怠管理・給与計算を
ラクにするクラウド型のシステムです。
- 従業員
- 従業員ごとに用意されたアカウントにログインし、打刻や勤怠申請を行います。
- 「楽楽勤怠」
- 勤怠情報をシステムで一元管理し、給与計算に必要なデータを自動集計します。
- 人事労務担当者
- システムからデータ出力して給与システムに連携するだけで簡単に給与計算を行うことができます。
出退勤や残業、休暇取得などの勤怠情報を一元管理し、給与計算に必要なデータを1クリックで出力します。
インターネットに接続可能なパソコンやスマートフォンがあれば外出時や在宅ワーク時にも利用可能です。
あなたの会社の働き方改革に貢献する勤怠管理システムです。
「楽楽勤怠」が
選ばれている理由

豊富な機能群
現状運用にあわせた課題解決や業務効率化を実現します。

初めても乗り換えも安心の、
専任サポート
※2024年3月末現在
ご要望に合わせてWEBでのご案内も可能です。
知りたい方はこちら

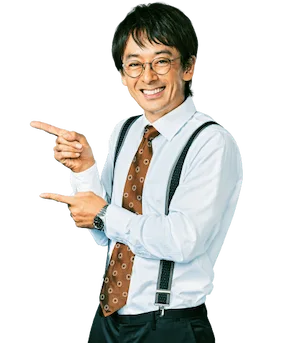
関連サービスのご紹介
「楽楽勤怠」の姉妹製品・関連サービスのご紹介です。
バックオフィス業務のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ83,000社以上のご契約をいただいています(※2024年3月末現在)。「楽楽勤怠」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。


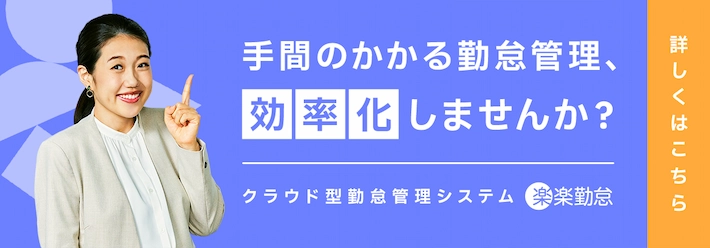
 とは
とは




