就業規則に沿った勤怠管理システムの運用方法と導入時にチェックすべきこと

勤怠管理システムは、従業員の労働時間や出退勤状況をデジタルで正確に記録・管理でき、勤怠管理の効率化に大きく役立ちます。
しかし、効果的に活用するためには、やみくもに導入するのではなく、自社の就業規則に沿った設定のもと運用することが大切です。
そこで本記事では、勤怠管理システムの効果を最大限高めるために、導入時にチェックしておきたい項目を解説していきます。
自社の就業規則に対応できるシステムを選んで、勤怠管理システムの導入成功へと導いていきましょう。
この記事の目次
就業規則とは?
就業規則とは、労働条件や職場でのルールなどを定めた規則集のことです。
常時10名以上の従業員を使用する企業の使用者は、法令や労働協約(※)に則って、必ず作成する必要があります。
就業規則には、以下のような項目についてまとめられています。
- 始業や終業の時刻
- 休憩時間
- 休日・休暇の規定
- 賃金の計算方法
- 退職手当
- 賞与
就業規則は、労働者と使用者の双方が守らなければならないルールです。
それぞれの権利や義務を明確にすることで、労使間(※)の無用なトラブルを防止します。併せて、全従業員への周知も法律によって定められているため、従業員の目につく場所への掲示や書面を交付するなどの対応も必要になります。
また、就業規則は一度策定して終わりではありません。法改正や時代の流れに応じて見直し、修正を加えながら更新していくことが求められます。
※(参考)厚生労働省「就業規則を作成しましょう」
※労使間:労働者(従業員)と使用者(企業・雇用主)の関係のこと
※労働協約:労働組合と使用者(企業)が労働条件や待遇について交わす正式な合意のこと
就業管理と勤怠管理の違い
就業規則に則したシステム運用のために、就業管理と勤怠管理の違いについて整理しておきましょう。
就業管理は、労働時間や雇用形態、給与計算、人事評価など、労務管理全般を指します。一方で勤怠管理は、その中でも『出退勤の記録・残業時間の管理・休暇の取得状況』など、勤務実態に特化した管理を指します。
就業管理は就業規則に沿って規定されており、適切に管理することで従業員のモチベーションや生産性の向上にもつながります。
一方の勤怠管理における勤怠状況の記録や保管は、労働基準法や厚生労働省が作成したガイドライン(※)によって定められているため、企業にとっては必須の業務です。
万が一違反すると、企業側に罰則が加えられることもあるので注意が必要です。
※(参照)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
勤怠管理システムの運用は就業規則に沿った設定が重要
勤怠管理システムを効果的に運用するには、あらかじめ自社の就業規則に従った設定を行う必要があります。
その理由は、就業規則に沿った設定を行うことで、法令遵守・労使トラブル防止・給与計算の正確性確保につながり、スムーズな勤怠管理が実現できるためです。
このときに気をつけなければならないのは、自社の就業規則が法令を遵守しているかどうかです。法令はしばしば改正されるため、そのつど就業規則も見直されているか、法令違反はないかを確認しておきましょう。
たとえば、就業規則では「1日の時間外労働時間は1分単位で計算する」と定めているのに、システムでは15分単位で切り捨てていた場合は、その分の残業代の未払いが発生するリスクがあります。
このようなリスクを回避するためにも、勤怠管理システムの設定を就業規則に沿って設定しておくことで、法令や就業規則を遵守した時間外労働時間集計ができます。
また、シフト制を導入している企業では、事前に労働日や労働時間の上限を設定しておくことで、就業規則や労働契約で定めた休日が確保できます。
このように、勤怠管理システムの設定と就業規則の整合性を確保することで、法令や就業規則の遵守はもちろん従業員の納得感も高まり、トラブルを未然に防ぐことができます。
就業規則に沿わない設定による勤怠管理システム運用の失敗例
勤怠管理システムの設定が自社の就業規則に適合していないと、労働時間の管理ミスや給与計算の誤りが発生し、結果として労使トラブルや法令違反のリスクが高まる可能性があります。
以下のケースは、就業規則とシステムの設定が一致していないことで起こりうる失敗例です。
- 残業時間の集計が正しく行われず、残業代の未払いが発生する
- フレックスタイム制の設定不備により従業員の混乱を招く
- 雇用形態ごとの労働時間設定ミスで労使トラブルにつながる
上記のような状態では、自社の就業規則遵守における管理を徹底できず、企業の健全な運営の妨げになります。また、労働基準法などの法律違反にも該当する場合、企業が管理義務を怠ったとして罰則が課されるリスクもあるでしょう。
こうした失敗を回避するためにも、勤怠管理システムの導入時には、自社の就業規則に応じた細かい設定を徹底することが重要です。
企業ごとの就業規則に沿った勤怠管理システムの設定と運用方法
ここでは、企業ごとの就業規則に沿った、勤怠管理システムの設定手順を解説していきます。
勤怠管理システム導入時の設定では、以下の項目を確認しながら自社に合わせてカスタマイズを行い、効果的な運用を目指しましょう。
勤怠データの集計方法の設定
はじめに勤怠データの集計ルールを設定します。
システムには「労働時間」「残業時間」「休暇」「出勤日数」「欠勤日数」などの計算方法を細かく設定することができます。
たとえば1か月における労働時間の端数処理では、「1分」「15分」「30分」など、企業が定める時間単位を設定可能です。
「法定残業時間」と「超過残業時間」の区別や計算方法、「有給休暇」の日数、「特別休暇」などの設定も可能です。
勤怠データの集計ルールは、就業規則や労働基準法などの法令に基づいていることが原則です。
システムによって集計ルールの対応範囲が異なるため、事前に確認しましょう。
残業時間の上限、申請・承認方法の設定
残業時間の上限管理や残業の申請・承認までの業務フローを、勤怠管理システムの設定によって一元管理できます。
残業時間を正確に管理することで残業代の未払いが防げるため、過重労働の把握も可能です。
就業規則で定める所定労働時間を超えていても、法定労働時間(1日8時間、週40時間)の範囲内であれば、割増賃金の対象にはなりません。
しかし、就業規則に特別な記載があれば、規則に合わせた設定が必要です。
雇用形態・勤務形態の違いにおける設定
「正社員」「派遣社員」「契約社員」「アルバイト」「パート」「インターン」など、雇用形態の設定も必要です。
それぞれで就業時間や休日が異なる場合は、雇用形態ごとに、定時開始時刻・終了時刻、直行直帰やリモートワーク時の扱いなど、勤務条件を細かく登録する必要があります。
従業員の勤務形態が複雑な場合は、それぞれの働き方に対して柔軟に対応できるシステムを選ぶとよいでしょう。
また、派遣社員から正社員へなど勤務形態が変わる場合には、システム上でも設定を変更する必要があります。
有給休暇の取得・消化管理の設定
有給休暇の設定を行うことで、「付与日数」「取得条件」「取得制限」「残数」などが管理でき、従業員はシステムを通して取得申請もできます。
労働基準法では、就業から半年を経過しており、なおかつ、そのうち8割以上勤務した場合に、有給休暇を原則10日間与えられる規定になっています。(※1)また、対象となる従業員に対して、企業は年間5日以上の有給を取得させる義務(※2)があるため、法令遵守の観点からもシステム上で休暇の管理ができる意義は大きいといえます。
有給休暇は、正社員やパートなど雇用形態に関わらず一定の条件を満たせば付与されなければなりません。
就業規則と併せて適用できているかどうかを確認しておきましょう。
※1(参照)厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
※2:雇用形態によって異なります
勤怠状況の監視とアラートの設定
長時間労働や欠勤などの異常を検知し、管理者や従業員に自動通知するアラート機能を用いることで、早期に問題を検知し、改善に役立てることができます。
あらかじめシステムに長時間労動や欠勤などの条件を設定しておくと、条件に抵触した場合にアラートが発せられます。これにより、問題が深刻化しないよう早目に必要な対策を打つことができるでしょう。
システムが勤怠状況を監視することで、労動災害を予防し、体調やメンタルの悪化リスクを抑えることができます。
このような勤怠管理システムの働きは、結果的に従業員の安全と健康を守ることにもつながります。
勤務制度に合わせた管理方法の設定
働き方が多様化されていく中、フレックスタイム制やシフト制、裁量労働制など、企業によって勤務制度にも違いがあります。
この場合、自社の勤務制度に合わせて勤務時間や残業、休暇などの管理方法を、勤怠管理システムへ細かく設定する必要があります。
基本的に固定時間制であれば、どのシステムでも対応可能ですが、社内に複数の勤務制度があったり独自の勤務体系があったりする場合は、カスタマイズ性の高いシステムを選ぶようにしましょう。
給与計算を行うための設定
自社の就業規則に沿って設定した勤怠管理システムに給与計算システムを連携させることで、従業員ごとの条件に応じて、自動で給与計算できます。
勤怠管理システムは、給与計算を行うためのベースとなるデータを管理しています。手当ごとの集計やプロジェクトごとの人件費管理など、自社のニーズを確認しておきましょう。
給与計算におけるミスは大きなトラブルの原因になることから、給与計算システムとの連携による自動化は、業務改善に大いに役立ちます。
また、経理担当者の負担も軽減でき、残業代の削減にもつながります。
勤怠管理システム導入前にチェックすべきポイント7つ
ここでは、勤怠管理システムの導入を成功させるために確認しておきたいポイントを7つ紹介します。
自社の就業規則を遵守しながら勤怠管理システムをより効果的に活用していくためにも、以下のチェックポイントを踏まえたうえでシステム選定に進みましょう。
それぞれの詳細について、以下で詳しく解説していきます。
①どんな目的で導入するのか
なぜ勤怠管理システムの導入が必要なのか、導入によりどんな勤怠管理課題を解決したいのか、といった導入の目的を明確にしましょう。
勤怠管理システム導入の目的を明確にすることで、自社の課題に合ったシステム選定につながり、業務効率化や法令に沿った就業規則遵守の実現性が高まります。
たとえば勤務形態の複雑化が勤怠管理の課題であれば、従業員ごとの勤務時間に柔軟に対応する自動計算機能があるシステムを選ぶことで、管理者の負担が軽減されます。
勤怠管理システムの導入目的を明確にしておくことで、自社に最適なシステム選定と適切な人事労務管理の実現につながります。
②自社の就業規則が法律に沿っているか
前記したように、勤怠管理システム導入の前には必ず就業規則を見直して、法令を遵守できているか確認しましょう。
勤怠管理システムの効果的な運用には自社の就業規則に沿った設定が必須ですが、そもそも就業規則が法律に準拠していなければ、正しい勤怠管理は行えません。
時代の流れとともに法律はたびたび改正されています。法改正に合わせて就業規則を更新していなければ、違反を犯してしまう可能性もあります。
いつ定められた就業規則なのか、いま手元にあるものは最新版なのかなど、慎重に確認しておきましょう。
ここで間違いがあると、システムの運用を始めてから大幅な修正が必要になり、業務を圧迫しかねません。リスク回避のためには丁寧な確認が重要です。
③設定変更やカスタマイズは可能か
勤怠管理システムを導入する際は、自社の就業規則を変更する場合も加味して、設定変更やカスタマイズが可能かを確認することが重要です。
法改正などに応じて就業規則を変更した際に、柔軟な設定ができないシステムでは運用に支障をきたす可能性があります。
たとえばフレックスタイム制を新たに導入する場合には、勤怠管理システムにおいて、コアタイム設定、シフト制の細かな勤務パターン登録、時間外労働のアラート設定などが必要です。
こうした機能を簡単に追加したり、修正したりできるのか、あらかじめ確認しておきましょう。
自社の勤怠管理ルールに変更や追加があった場合にも柔軟に適応できるシステムを選ぶことで、スムーズな運用と法令遵守を実現できます。
④管理者・従業員どちらも使いやすいか
管理者も従業員も、双方にとって操作性のよいシステムを選ぶことが重要です。
直感的に扱えるものだと、システムに苦手意識を持つ従業員もスムーズに扱うことができるでしょう。その結果、システムに関する問い合わせが少なければ、管理者や人事労務担当者の負担も軽減できます。
また、操作が簡単ならば従業員のシステム利用が習慣として定着しやすく、打刻忘れがなくなったり休暇の取得率が向上したりすることが考えられます。
勤怠管理システムは、全従業員が積極的に活用して初めて最大効果を発揮します。
だからこそ、使いやすさは欠かせないポイントです。
⑤導入・運用コストは適切か
勤怠管理システムを導入する際には、初期費用に加えて毎月の利用料などがかかるため、そのコストが適切かどうか機能とコストとのバランスを確認するようにしましょう。
企業規模に見合ったシステムなのか、自社の勤務形態がシステム導入に適しているのなど、費用対効果を見積もってみてください。
また、給与計算や経費精算などのシステムをすでに利用している場合は、それらと連携できるかどうかを必ず確認しておくことも大切です。
せっかく導入しても連携できなければ、効率化につながらない可能性があります。
⑥サポート体制が充実しているか
勤怠管理システム導入時の設定に加え、本格運用においても、システム提供会社からどのようなサポートが受けられるのか事前にしっかり調べておきましょう。
いざシステムを使ってみたら、設定が違っていたり、操作がわからなくなったりする可能性もあるからです。
トラブルがあったときは、やはりサポートに頼ることになります。しかし、提供会社の対応がメール限定だったり、有料だったりというケースもあります。
法改正に伴ってシステムはアップデートされるのか、スピード感のある対応が受けられるのかなど、システムを選ぶ際には具体的なサポート体制まで確認しておくことをおすすめします。
⑦導入時にテスト運用期間が設けられているか
運用上のエラーや予期せぬトラブルを防ぐために、本格導入前にテスト運用の期間が設けられていると安心です。
特に出退勤時の打刻は、全社員が習慣的にできなければ意味がありません。試用期間を利用して、活用の定着が図れる運用になっているかをチェックしてみてください。
全社展開を急ぎすぎると、使いこなせない社員へのフォローがおろそかになり、システムが浸透しない原因となります。
企業規模が大きい場合は、一部の部署に先行導入して、従業員の反応を確認してみるのもひとつの手といえます。
従業員の利用状況を見ながら運用方法を修正し、システム導入のメリットを全社員で共有できるよう進めていきましょう。
勤怠管理システム導入時は従業員への周知と活用教育も徹底しよう
勤怠管理システムの導入が決まったら、全社員に向けて素早く周知を図り、得られるメリットを説明しましょう。
勤怠管理システムは人事労務管理担当者だけが扱うものではなく、全従業員が毎回適切に使ってこそ効果が得られるものです。
もしもシステムに苦手意識があったり、ルーティン作業の変更に抵抗感があったりする従業員がいる場合には、丁寧な事前説明が導入成功の秘訣です。
具体的には、マニュアルを作成したり、説明会や研修を行ったりして、操作方法を共有しておくことが大切です。また、不明点があれば個別に対応するなど細やかにフォローできればなおよいでしょう。
「説明したのだから理解できているはず」という思い込みで進めると、トラブルのもとになるので気をつけてください。
導入メリットの最大化を図るためには、従業員の協力が必須です。
運用後には、従業員からのフィードバックを集め、課題が見つかれば改善し、全社員への浸透を目指しましょう。
クラウド型勤怠管理システム「楽楽勤怠」は企業ごとの就業規則に合わせて勤怠管理を効率化します
ここまで、勤怠管理システムのより効果的な活用を目指すなら、就業規則に沿った設定ができるシステム選びが鉄則であることを解説してきました。
このとき、就業規則自体に法令違反があると後にトラブルとなることから、就業規則の見直しも忘れてはいけません。
自社の就業規則に合ったシステムを導入できれば、勤怠管理や関連業務は大幅に効率化できます。また、管理者と従業員との間で課題共有が進んで、より強固な協力関係の構築にもつながるでしょう。
株式会社ラクスが提供するクラウド型勤怠管理システム「楽楽勤怠」は、企業の独自ルールにも柔軟に対応できる豊富な機能を搭載しています。
システム導入時には専任の担当者がつくので、初めてのシステム導入でも安心です。
自社の就業規則に沿った運用ができるかを確認した場合も、お気軽にお問い合わせください。貴社のご希望を丁寧にお聞きし、最適な選択ができるようサポートいたします。
メールで受け取る

働き方改革関連法へ対応!勤怠管理システム「楽楽勤怠」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
- 監修楽楽勤怠コラム編集部
- 「楽楽勤怠」コラム編集部です。
人事労務担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報をお届けしています。
https://www.rakurakukintai.jp/
こんなお悩みありませんか?
そのお悩み で解決できます!
で解決できます!

実際のシステム画面をお見せしながら
現在の運用方法についてお伺いし、
貴社に合わせた運用提案を
させていただきます。
ご要望に合わせてWEBでのご案内も可能です。
知りたい方はこちら

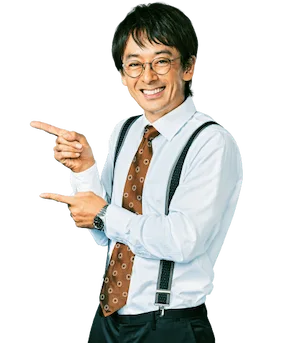
 とは
とは
「楽楽勤怠」は勤怠管理・給与計算を
ラクにするクラウド型のシステムです。
- 従業員
- 従業員ごとに用意されたアカウントにログインし、打刻や勤怠申請を行います。
- 「楽楽勤怠」
- 勤怠情報をシステムで一元管理し、給与計算に必要なデータを自動集計します。
- 人事労務担当者
- システムからデータ出力して給与システムに連携するだけで簡単に給与計算を行うことができます。
出退勤や残業、休暇取得などの勤怠情報を一元管理し、給与計算に必要なデータを1クリックで出力します。
インターネットに接続可能なパソコンやスマートフォンがあれば外出時や在宅ワーク時にも利用可能です。
あなたの会社の働き方改革に貢献する勤怠管理システムです。
「楽楽勤怠」が
選ばれている理由

豊富な機能群
現状運用にあわせた課題解決や業務効率化を実現します。

初めても乗り換えも安心の、
専任サポート
※2024年3月末現在
ご要望に合わせてWEBでのご案内も可能です。
知りたい方はこちら

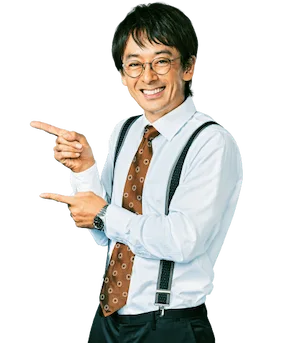
関連サービスのご紹介
「楽楽勤怠」の姉妹製品・関連サービスのご紹介です。
バックオフィス業務のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ83,000社以上のご契約をいただいています(※2024年3月末現在)。「楽楽勤怠」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。


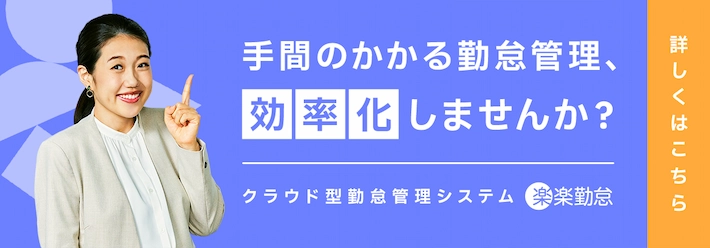
 とは
とは




