勤怠管理の課題と解決策とは?勤怠管理システム導入のメリットも解説

政府が推進する働き方改革(※)の影響もあり、働き方はますます多様化しています。こうした中、働く時間や場所の選択肢が増えるにつれ、勤怠管理に課題を感じる企業担当者も多いのではないでしょうか。
これまで幅広い企業で用いられてきたタイムカードやExcelによる勤怠管理は、一定の柔軟性と実績がある一方で、働き方の多様化に対応しきれない場面も増えてきました。
そこでおすすめの解決策が、勤怠管理システムの導入です。勤怠管理システムでは、従業員ごとの働き方に合わせた勤怠データの自動集計や、効率的な管理が実現できます。
この記事では、勤怠管理の課題を明らかにするとともに、その解決策としての勤怠管理システム導入メリットや、選定時のチェックポイントについて詳しく解説します。
※(参考)厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~」
この記事の目次
適切な勤怠管理が必要とされるわけ
勤怠管理とは、企業が従業員の労働時間や休暇の取得状況などを適切に把握・管理することをいいます。
企業が従業員に適切な給与を支払うためにも、その前提として勤怠管理が適切に行われることが不可欠です。
また、勤怠管理の目的は、給与計算を正しく行うだけにとどまりません。
働き方改革関連法の施行による勤務形態の柔軟化にともない、企業にとって個々の従業員の労働時間や休暇の取得状況の把握はより難しくなっています。その風潮を受け、従業員の心身の健康を守るため、そして法令を遵守するためにも、勤怠管理の重要性がより高まっているのです。
ここでは改めて、勤怠管理が必要とされる理由について掘り下げてみましょう。
従業員の心身の健康を守るため
適切な勤怠管理を行うことは、従業員の健康を守るためにも重要です。
労働時間を正確に把握することで、長時間労働や過労につながる従業員をあらかじめ把握し、対策を打つことで未然に防ぐことができます。
これにより、従業員が適切な休息を取ることができ、肉体的・精神的な健康を維持することが可能です。
また、過剰な残業が発生している場合、早期に気づき対応することで過労死やメンタルヘルス不全を防ぐことができるでしょう。
正しく給与計算を行うため
正しい給与計算をするためには、前提として勤怠管理が正しく行われていることが必要です。
給与は勤怠データをベースに算出されるため、適切な勤怠管理が実施できていない場合、企業が従業員へ支払う給与に過不足が生じる可能性があります。
たとえば従業員の労働時間や残業時間、有給休暇の取得状況などを正確に把握しておかないと残業代の支給が不足する事態につながるでしょう。
勤怠管理を適正に行うことで、はじめて実態に即した正しい給与計算が可能となるのです。
法令を遵守するため
適切な勤怠管理は、法令を遵守するためにも重要です。
企業は労働基準法をはじめとする労働関連の法令を遵守した運営が求められており、適切な勤怠管理により、従業員の労働時間や休日・休暇などを正しく把握する必要があります。
また2019年4月から順次施行された「働き方改革関連法」にともない、長時間労働の是正や労働環境の改善を目的とした「改正労働基準法」が施行されたことで、法令遵守のための適切な勤怠管理の必要性は一層高まっています。(※)
改正労働基準法の主な内容は、以下の通りです。
- 時間外労働の上限規制:月45時間、年360時間を原則として時間外労働の上限を設定
- 年次有給休暇の確実な取得:10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について確実に取得させなければならない
- 時間外労働に対する割増賃金率の引上げ:月60時間を超える中小企業の時間外労働に対する割増賃金を50%に引上げ
適切な勤怠管理の徹底は法令遵守のために必須であり、知らず知らずのうちに法令違反を犯してしまうリスクの回避にもつながります。
※(参照)厚生労働省「働き方改革関連法に関するハンドブック」
勤怠管理のよくある課題とは?
勤怠管理の方法に、紙のタイムカードやExcelを主体に用いている企業はまだまだ少なくありません。
この場合、従業員から申告されたデータを締め日の後に入力・集計し、管理していることになりますが、この手法における主な課題には、以下が挙がります。
自社の勤怠管理状況と照らし合わせながら、解決すべき課題があるか確認していきましょう。
①打刻ミス、不正申告のリスクがある
紙のタイムカードやExcelによる勤怠管理のよくある課題として、打刻ミスの発生や不正申告のリスクが挙がります。
紙やExcelへの手作業による入力が必要なため、記入漏れなどのヒューマンエラーが発生しやすく、打刻ミスにつながりやすいでしょう。
また、打刻実施は従業員ごとにゆだねられているため、実際の労働時間よりも前後した時間で打刻したり、ほかの従業員になりすまして不正打刻することも可能です。さらには、履歴も追いづらく、後からトラブルになることもあります。
このように、紙のタイムカードやExcelによる勤怠管理は正確性においての課題があるため、人的ミスや不正のリスクが高いという課題があります。
②勤怠データの集計・確認に時間と労力が必要
勤怠データが紙などのアナログ的な手法で管理されている場合、それを漏れなく回収して転記する工程からスタートするため、集計や確認作業に労力が必要です。
勤怠管理では、従業員ごとに打刻した始業・就業時間から労働時間を記録し、所定時間外労働が発生している場合や休暇を取得した場合なども含めてデータをまとめます。
それを集計・確認したうえで給与を計算することになりますが、手作業が多く発生すればするほど、手間も時間もかかってしまいます。
③正確な勤務状況をリアルタイムに把握しにくい
紙やExcelによる勤怠管理だと、個々の従業員ごとにどのくらい残業が増えているのか、有給休暇がきちんと取得できているのかなどの状況がリアルタイムで把握しにくいというデメリットがあります。
紙やExcelによる勤怠管理の場合、データ集計が月末などの勤怠締めのタイミングに偏りやすく、日々の状況把握が困難になることがあるでしょう。
勤怠状況のリアルタイムな把握が困難な場合、残業の急増や有給未消化といた問題に早期対応できないリスクが生じます。
④法改正や新制度に素早く対応しにくい
紙のタイムカードやExcelによる勤怠管理では、法改正が行われた際に即座に対応するのは簡単ではありません。
特に労働時間の管理や残業規制、休暇取得に関する変更などがあると、制度変更に伴う管理ルールの修正を手動で行う必要があり、設定変更や社内展開に時間と手間がかかります。
近年では働き方改革の影響による法改正や企業ごとの制度見直しも見られているため、こうした制度変更へのスピーディな対応が難しい点は、手動での勤怠管理の大きな課題だといえます。
⑤多様な働き方への対応が難しい
時間や場所を選ばない柔軟で多様な働き方が増えている昨今、手動による勤怠管理では対応が難しい場面が増えています。
たとえば紙のタイムカードやExcelでの管理では、フレックスタイム制やリモートワークなど、異なる勤務時間や場所で働く従業員の勤怠データを一元的に把握するのが難しいといえます。
こういった従業員ごとの多様な勤務形態に合わせて勤怠データを手動で集計し計算するには、多くの手間と時間がかかり、人事労務担当者の負担も大きいでしょう。
従業員ごとの多様な働き方に対して柔軟に勤怠管理できない場合、従業員の働きやすさや企業の効率的な運営に支障をきたす可能性が出てきます。
⑥適正な人材配置に手間がかかる
適材適所の人材配置をする上でも、手動による勤怠管理では多くの課題があるといえます。
勤怠データの収集や分析にどうしても時間がかかってしまうことから、人材配置への迅速な意思決定が妨げられ、企業全体の生産性や効率の低下につながるおそれも出てくるでしょう。
さらに、紙のタイムカードやExcelでの勤怠管理では、勤怠データへ従業員のスキルや業務パフォーマンスに関するデータをかけ合わせて一元的に把握することが困難です。そのため、個々の従業員の強みや適性を正確に評価しにくく、最適な配置や役割分担を行うことが難しくなります。
このように、従業員ごとの勤怠状況を把握しずらく、人材配置に手間がかかる部分はよくある勤怠管理の課題です。
⑦タイムカードの保管・移送にコストがかかる
勤怠管理でタイムカードを使用している場合には、カードの保管や移送に多大な時間やコストがかかります。
まず、タイムカードを物理的に保管するためには専用の収納スペースが必要となり、保管場所の確保や整理整頓の手間がかかります。
またタイムカードを各事業所・オフィスや部門から集めるために、移送の手間や人件費、タイムラグも発生します。
加えてタイムカードの移送中に紛失や破損のリスクもあり、勤怠管理そのものが正しく行えなくなってしまうことにもつながります。
勤怠管理の課題を解決する方法
勤怠管理の課題を解決するためには、いくつかの対策が考えられます。
たとえば、自社の就業規則を見直して現行のルールを改善することや、対応する人員を増やして業務負担を軽減すること、勤怠管理システムを導入する方法の大きく3点が挙げられます。
それぞれにメリット・デメリットをまとめたものは下表のとおりです。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 1.就業規則の見直し | ・実態に即した勤怠ルールにできる |
・手続きに時間がかかる ・適切に運用しないと解決しない ・手動管理のリスクは残る |
| 2.人員の増加 |
・業務の処理スピードが向上する ・ミスが軽減する ・従業員からの問い合わせに迅速に対応できる |
・人件費が増加する ・業務フローが複雑化する ・情報共有や連携の手間が増える ・属人化しやすく根本的な効率化にはつながらない可能性 |
| 3.勤怠管理システムの導入 |
・勤怠データの集計管理を自動化できる ・長期的なコスト削減効果がある ・リアルタイムで勤怠状況を把握できる ・ミスを減らし法的リスクを削減できる |
・導入コスト・ランニングコストがかかる ・自社にマッチしたシステム構築が必要 |
それぞれの方法にメリット・デメリットはありますが、総合的に比較してみると、勤怠管理システムを導入することで、大きな工数削減・ミス削減効果が期待できるといえるでしょう。
導入時の初期投資は一定のまとまった費用がかかりますが、自社にマッチしたシステムを精査して導入すれば、長期的に回収できるほどの費用対効果は見込めるはずです。
勤怠管理システム導入が課題解決に寄与する理由7選
これまで従来型の勤怠管理のさまざまな課題について検討してきましたが、これらを解決するためには勤怠管理システムの導が有効です。
それがどんなメリットをもたらすのか、具体的に以下の7つの項目について見ていきましょう。
①勤怠データの集計や計算を自動化できる
勤怠管理システム導入により、勤怠データの集計・計算が自動化されます。
それにより、これまで手作業で行ってきた入力や転記・集計の際に発生するミスを防ぎ、迅速かつ正確なデータ管理をすることができます。
また、勤怠管理システムと給与計算システムを連携させることで勤怠データが自動的に給与計算に反映され、スムーズな給与処理が可能です。
管理業務の負担が軽減されるだけでなく、適切な給与計算により法令遵守の徹底も図れます。
②正確な打刻データが得られる
勤怠システムの導入により、打刻ミスや不正打刻を防ぎ、正確な打刻データが得られます。
タイムカードやExcel管理簿による勤怠管理であれば、第三者によるなりすましや打刻時間をずらすなどの不正を見抜くことは困難です。
一方、勤怠管理システムであれば、打刻時にIDや生体認証(指紋や顔認証など)を利用するため打刻ミスが減少し、打刻者本人を確実に特定することができます。
これにより、代理打刻や不正な時間操作が防げ、労働時間を正確に記録することが可能です。
③勤怠状況をリアルタイムに把握できる
勤怠管理システムは、従業員の出退勤時間をデジタルデータとして瞬時に記録していくため、リアルタイムに勤怠状況を把握することが可能です。
従来のアナログな勤怠管理の方法だと、「締め日を迎えて計算してみたら残業の上限を超えてしまった」などといったケースも起きかねません。
しかし、勤怠管理システムは事前にアラートを発信するなどで長時間労働を未然に防ぐこともできます。
また、残業時間や有給休暇などの取得状況も自動的に記録・管理するため、労務管理担当者にとって従業員の勤怠状況をトータルで管理することが容易です。
④法改正へスピーディに対応できる
勤怠管理システムの導入により、アップデートを通じて法改正に則った勤怠管理を迅速に行うことが可能となります。
法令が改正された場合、アナログ管理では運用変更や修正対応を手作業で行う必要がありますが、システムであればアップデートするだけで新しい規定へ自動的に対応することができます。
これにより手動での規則変更や複雑な調整が不要となり、法令遵守をスピーディに、より確実に実現することができるでしょう。
⑤多様な働き方に対応可能
勤怠管理システムは、フレックス制やリモートワークなど多様な勤務形態に対応します。従来のタイムカードやICカードに加えてスマートフォンやPCを利用したWeb打刻が可能なため、出社しない従業員であっても、自宅や外出先から労働時間を正確に記録することができます。
結果として、従業員は柔軟な働き方を選ぶことができ、企業も多様な勤務形態に対応した効率的な勤怠管理を行うことが可能となります。
⑥シフト管理機能で人材配置がスムーズに行える
シフト管理機能が搭載されている勤怠管理システムであれば、従業員の勤務希望やスケジュールを一元管理し、適切なシフトを自動で作成できるためスムーズな人材配置が可能です。
これにより管理者は手作業でシフトを組む手間が省け、従業員の勤務状況や希望を考慮した効率的な人材配置が可能となるでしょう。また、急なシフト変更や欠員にも迅速に対応できます。
勤怠管理システムによってはオプション機能として付加できる場合もあるので、シフト管理に日々悩んでいる人事労務管理担当者の方はぜひチェックしてみてください。
⑦タイムカードの保管や移送の負担がなくなる
勤怠管理システムの導入によりペーパーレス化が一気に進み、紙の保管や整理、移送に関わる手間とコストを大幅に削減することができます。
紙のタイムカードや出勤簿が不要となり、労働時間や休暇の記録がすべてデジタル化されます。そしてデジタル化されたデータは検索や分析もしやすいため、管理業務の効率もアップします。
さらに、ペーパーレス化は環境負荷の低減にもつながり、企業のエコフレンドリーな取り組みを強化することができます。
勤怠管理システムの導入における注意点4つ
勤怠管理システムの導入メリットについて記述してきましたが、デメリットがまったくないわけではありません。
自社にとって最適なシステムを導入するためにも、コスト面や運用面での課題についてあらかじめ知っておくことが重要です。
以下4つのポイントに分けて解説していきます。
①導入と運用にコストがかかる
勤怠管理システムの導入には、初期導入コストや運用・保守費用がかかります。
特に初期費用、具体的にはシステムの購入や設定、カスタマイズにはまとまった金額の初期投資が必要であり、企業規模や業種によっては導入に負担を感じる場面もあるのではないでしょうか。さらに、システムの運用には定期的なメンテナンスやアップデートが不可欠で、これにも追加コストが発生します。
一方で、勤怠データの自動集計や計算などによる大幅な業務効率化につながり、人事労務担当者がより優先度の高い業務に集中できることによって企業のさらなる利益拡大を目指すこともできるでしょう。
勤怠管理システムにかかるコストだけでなく、導入した場合にどんな効果や利益が得られるのかを総合的に判断し、導入を検討しましょう。
②自社の就業ルールに適応しない場合がある
ひと口に勤怠管理システムといっても多種多様であり、自社の就業ルールに必ずしもフィットしない場合があります。
多くのシステムは基本的な勤怠管理の項目に対応していますが、企業ごとのオリジナルな勤務形態や、特殊な就業規則が設けられている場合などに対応しきれないようなこともあるでしょう。
適応しない場合は別のシステムを検討するか、あるいはシステムをカスタマイズする必要があり、その分の追加コストや導入時の設定工数が発生する可能性があります。
勤怠管理システムの導入を検討する際には、事前にデモ機能やお問い合わせを活用するなどして、自社の就業ルールに問題なく適応するのかを確認しておきましょう。
③運用ルールと操作方法を全社的に浸透させる必要がある
勤怠システムの導入にあたっては、管理する側の担当者はもちろん、実際に使うすべての従業員に運用ルールと操作方法を理解してもらう必要があります。
新しいシステムを効果的に使いこなすためには、全従業員が共通ルールのもとで正確に操作できることが不可欠です。
それには、従業員への研修やマニュアルの作成・配布、サポート体制の整備が必要でしょう。
システムに対する理解の浸透が不十分だと、システム導入の効果が発揮されず、逆に混乱やミスが生じる可能性が出てくるので注意が必要です。
④収益向上への影響が見えにくい場合がある
勤怠管理システムを導入した際、収益向上への直接的な影響が見えにくい場合があるでしょう。
その理由は、勤怠データ集計ミスの削減・管理業務の効率化・長時間労働の改善といった効果は「間接改善」であり、売上アップのような「目に見える成果」として数値化しにくい傾向があるためです。
勤怠管理システムの導入効果を測る際には、導入前後で業務時間をどの程度削減できるのかといった定量的な比較を行い、導入メリットを確認してみましょう。
また、「業務のストレスが減った」「業務効率化への意識が高まった」など、管理者と従業員双方で感じられる定性的な導入価値も加味して導入効果を検討することをおすすめします。
勤怠管理システム導入における7つのチェックポイント
ここまで、勤怠管理システムのメリットとデメリットを見てきました。
コスト面・運用面などのさまざまなメリット・デメリットを踏まえたうえで、実際に勤怠管理システムを導入検討する際に注意すべき以下の7つのポイントについて解説していきます。
①自社の就業ルールに合っているか
勤怠システムの導入に際しては、自社の就業ルールに適合しているかを確認することが重要です。
システムが自社の勤務形態や特殊な就業規則に対応しているかどうかを事前に検証し、必要に応じてカスタマイズが可能かを確認しましょう。
もし自社のやり方にマッチしていない場合、せっかくのシステムの効果が十分に発揮されず、かえって管理が複雑になってしまうリスクがあります。
自社の就業ルールにあっているかどうかの確認には、デモ機能の活用や、お問い合わせによる相談がおすすめです。
導入前の慎重な検討と確認が、勤怠管理システムの運用成功の鍵となります。
②給与計算システムと連携可能か
勤怠管理システムの導入にあたっては、自社で使っている給与計算システムと連携が可能かをチェックすることが重要です。
スムーズに連携できれば勤怠データは自動的に給与計算システムに反映され、給与計算業務が一気に効率化されるでしょう。
これまで手作業で行っていた入力・転記・集計にかかっていた時間や工数を大幅にカットできるだけでなく、ミスを防ぐことができるため、正しい給与計算が実現できます。
ぜひシステム導入前に連携の可否を確認しましょう。
③従業員が簡単に使用できるか
導入する勤怠管理システムを、従業員も簡単に操作できるかどうかは非常に重要なポイントです。
全従業員が毎日利用するものなので、打刻や申請が複雑で使いにくいと入力ミスや打刻忘れが増え、管理効率が低下してしまうおそれがあります。
直感的な操作性やわかりやすいインターフェースを持つシステムを選ぶことで従業員の負担を減らし、正確な勤怠管理が可能となります。
導入前にはぜひ実際のシステムのデモ画面を確認し、従業員がスムーズに利用できるかをチェックしましょう。
④セキュリティ・サポート体制はどうなっているか
勤怠管理システムの導入に際しては、セキュリティとサポート体制がどうなっているかも重要なポイントです。
システムには従業員の個人情報や勤怠データが含まれるため、セキュリティが脆弱だと不正アクセスやデータ漏洩のリスクが高まります。
また、システムの運用中に何らかのトラブルが発生した場合、サポートが受けられるかどうかも重要です。さらに、導入時や初期設定の段階から手厚いサポートがあるとスムーズな活用につながるでしょう。
強固なセキュリティと充実のサポート体制を備えたシステムを選ぶことで、安心して運用することができるのではないでしょうか。
⑤得られる効果と導入コストが見合っているか
得られる効果とコストという費用対効果も、勤怠管理システム導入における重要なポイントです。
導入にあたっては、まとまった金額が初期導入コストとしてかかりますし、その後の運用・保守費用も発生します。
そのため、投資がどれだけの効果を生むかの慎重な検討が必要です。
システムによる業務効率化やミス削減、法令遵守によるリスク回避など、具体的なメリットとコストを比較し、費用対効果がどれほどのものになるかを確認しておきましょう。
⑥将来の運用を見据えたカスタマイズが可能か
勤怠システムの導入に際しては、将来の運用を見据えたカスタマイズが可能かどうかを見極めておきましょう。
働き方の多様化などにより、勤怠管理のニーズは将来にわたって変化する可能性があります。
そのため、今のルールにはマッチしていても、今後の変化に備えてシステムが柔軟にカスタマイズできるか、必要に応じて機能追加や変更が可能かを確認することが重要です。
将来的な運用を見据えたカスタマイズ対応が可能なシステムを選ぶことで、長期的に効率的で適切な勤怠管理が可能となります。
⑦本格運用までに試用できるか
本格的に勤怠管理システムを導入する前に、試験的に運用できるかどうかをチェックしておきましょう。
一部の部署などでフィジビリティ(実現可能かどうか)導入を行うことで、そのシステムが自社のルールや業務フローにマッチするかを確認するとともに、従業員が操作に慣れる期間を設けることができます。
また試験導入中に課題が発見された場合、本導入までに改善することでスタート時のトラブルを防ぎ、スムーズな運用が可能になるでしょう。
試験導入の可否を確認し、リスクを最小限に抑えることが成功の鍵といえます。
クラウド型勤怠管理システム「楽楽勤怠」で人事労務管理の課題を解決しよう
この記事では、勤怠管理の意義や目的について確認したうえで、勤怠管理のよくある課題について考察してきました。 打刻ミスや不正申告のリスクがあること、勤怠データの集計・確認に手間と時間がかかること、正確な勤務状況を正確リアルタイムに把握しにくいなどの課題点により、紙のタイムカードやExcelによる勤怠管理には、多様化する働き方に対応しきれない部分があることがお分かりいただけたかと思います。 こうした課題を解決するために、ご検討いただきたいのが、ラクスが提供するクラウド型勤怠管理システム「楽楽勤怠」です。 「楽楽勤怠」は、豊富な機能と充実したサポートで、勤怠管理の効率化と企業の法令遵守に大きく貢献いたします。 自社の勤怠管理課題を解決したいとお考えの際には、ぜひ一度お問い合わせください。
メールで受け取る

働き方改革関連法へ対応!勤怠管理システム「楽楽勤怠」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
- 監修楽楽勤怠コラム編集部
- 「楽楽勤怠」コラム編集部です。
人事労務担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報をお届けしています。
https://www.rakurakukintai.jp/
こんなお悩みありませんか?
そのお悩み で解決できます!
で解決できます!

実際のシステム画面をお見せしながら
現在の運用方法についてお伺いし、
貴社に合わせた運用提案を
させていただきます。
ご要望に合わせてWEBでのご案内も可能です。
知りたい方はこちら

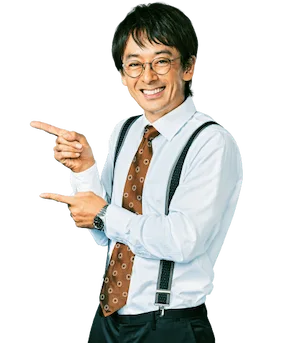
 とは
とは
「楽楽勤怠」は勤怠管理・給与計算を
ラクにするクラウド型のシステムです。
- 従業員
- 従業員ごとに用意されたアカウントにログインし、打刻や勤怠申請を行います。
- 「楽楽勤怠」
- 勤怠情報をシステムで一元管理し、給与計算に必要なデータを自動集計します。
- 人事労務担当者
- システムからデータ出力して給与システムに連携するだけで簡単に給与計算を行うことができます。
出退勤や残業、休暇取得などの勤怠情報を一元管理し、給与計算に必要なデータを1クリックで出力します。
インターネットに接続可能なパソコンやスマートフォンがあれば外出時や在宅ワーク時にも利用可能です。
あなたの会社の働き方改革に貢献する勤怠管理システムです。
「楽楽勤怠」が
選ばれている理由

豊富な機能群
現状運用にあわせた課題解決や業務効率化を実現します。

初めても乗り換えも安心の、
専任サポート
※2024年3月末現在
ご要望に合わせてWEBでのご案内も可能です。
知りたい方はこちら

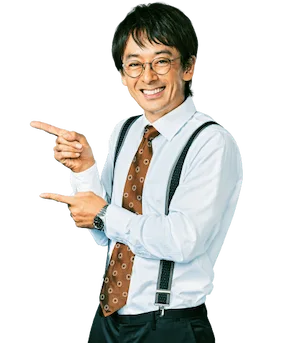
関連サービスのご紹介
「楽楽勤怠」の姉妹製品・関連サービスのご紹介です。
バックオフィス業務のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ83,000社以上のご契約をいただいています(※2024年3月末現在)。「楽楽勤怠」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。


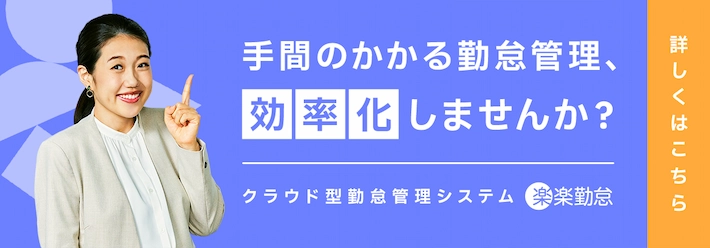
 とは
とは




