年次有給休暇管理簿は義務?罰則、保管期間、管理方法【社労士解説】

法定三帳簿と呼ばれる「賃金台帳」「労働者名簿」「出勤簿」の他にも、年次有給休暇管理簿を作成する義務があることはご存じでしょうか。
2019年4月から、年次有給休暇管理簿の作成と保存が義務付けられています。
従業員の年次有給休暇を適切に管理するためにも、記載しなければならない内容や保存期間を今一度おさらいしましょう。
この記事の目次
年次有給休暇管理簿とは何か

「年次有給休暇管理簿」(通称、年休管理簿)とは、年次有給休暇を取得した日付(時季)や取得した日数、付与した日(基準日)を労働者ごとに明らかにした書類です。2018年4月から法令により使用者に作成と保存が義務付けられています。(※1)
そもそも年次有給休暇は、労働者が心身のリフレッシュを図ることを目的として取得できる休暇です。そのため、原則として労働者が請求した時季に与える必要があります。企業は、事業の正常な運営を妨げる場合、取得時季の変更はできますが、取得を拒否することはできません。
しかし、労働者が「他の従業員に迷惑をかけたくない」と気兼ねしたりためらったりすることもあり、取得率が低調な状態にあることが問題となっていました。そういった背景を経て、2018年に働き方改革関連法が成立し、労働基準法が改正されました。2019年4月からは、すべての企業を対象に年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して年5日の年次有給休暇を取得させることが義務付けられています。(※2)
従業員の年次有給休暇の取得状況を正確に把握していなければ、年5日の取得ができているかを管理することはできません。従業員へ確実に年次有給休暇を取得させるためにも、年次有給休暇管理簿を必ず作成しましょう。
作成や提出を怠ると違法になる?罰則は?
年次有給休暇管理簿を作成しなかったことによる、直接的な罰則はありません。ただし、有給休暇が年10日以上付与されている労働者に対し、5日の取得がなかった場合は罰則として30万円以下の罰金が科されます。もちろん、年次有給休暇管理簿は法律上、就業規則等と異なり届け出義務はありません。とはいえ、作成および保管が義務付けられていますので、未対応の場合は是正指導の対象となります。また、年次有給休暇管理簿があることで、誰が5日取得義務に対してどの程度の取得日数が不足しているのかを認識できる帳票となります。そのため、法令順守だけでなく副次的に長時間労働の抑制にも寄与するものです。年次有給休暇管理簿には労働時間、休憩、休日が適用除外されている管理監督者も含めて備付が義務づけられています。管理監督者は対象とならないと誤認されているケースもありますが、管理監督者であっても年次有給休暇(他には深夜割増)は適用除外されていませんので、留意が必要です。
- (参考):川崎北労働基準監督署
年次有給休暇管理簿の保管期間

消滅時効の改正などを内容とする2020年4月1日施行の改正民法(※)に合わせて、労働基準法も改正されています。労働基準法上における賃金請求権の消滅時効の期間や賃金台帳などの記録の保存期間などが5年になりました。
しかし、当分の間、改正前における賃金台帳などの記録の保存期間に合わせて3年とする経過措置が設けられています。年次有給休暇管理簿についても同様の改正が行われ、年次有給休暇を与えた期間(基準日から1年間)とその期間満了後3年間は保存しなければなりません。
- (参考):法務省「民法(債権法)改正パンフレット」
年次有給休暇管理簿の内容
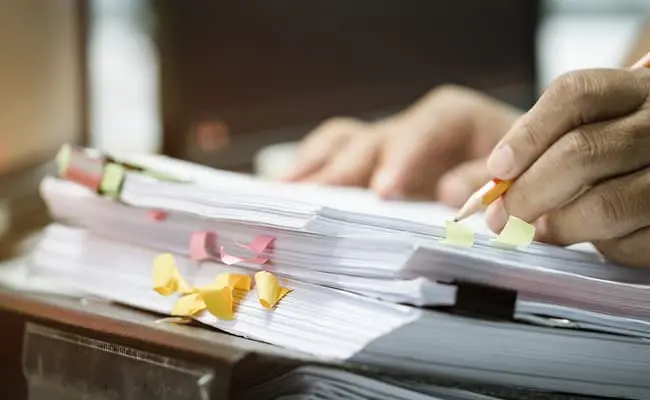
労働基準法施行規則第24条の7の条文を見てみましょう。
使用者は、法第39条第5項から第7項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第1基準日及び第2基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第55条の2及び第56条第3項において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後5年間保存しなければならない
<出典:e-Gov>
対象者や記載事項について具体的に解説します。
対象者
「法第39条第5項から第7項までの規定により有給休暇を与えたとき」とあるように、対象者は年次有給休暇が与えられた労働者であり、正社員だけではなく、パート・アルバイト、有期雇用の従業員も含まれます。
対象者には、管理監督者も含まれています。労働基準法上の管理監督者は、労働時間・休日・休憩の規定は適用されませんが、深夜および年次有給休暇の規定は適用されますので注意が必要です。
年次有給休暇管理簿は、労働者ごとに作成する必要があります。
入社して6ヵ月に満たないような年次有給休暇が与えられていない従業員については、作成の義務はありません。しかし、実務的には、年次有給休暇を取得した時点で管理簿を作成し始めることは現実的ではありません。少なくとも初めて年次有給休暇が付与される基準日までには作成するのがよいでしょう。
必要項目、書き方
「時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類」とあるように、「時季」「日数」「基準日」の3つが必要最小限の記載事項となります。
①「時季」:実際に年次有給休暇を取得した日
1日であれば「〇月〇日」と記載します。連続して取得したときには「〇月〇日から〇月×日まで」と記載しても「〇月〇日から×日間」と記載しても問題ありません。「1日単位の取得か」「半日単位(0.5日)の取得か」についても把握できるように記載しましょう。
②「日数」:基準日から1年間に実際に取得した日数
1日であれば「〇月〇日」と記載します。連続して取得したときには「〇月〇日から〇月×日まで」と記載しても「〇月〇日から×日間」と記載しても問題ありません。「1日単位の取得か」「半日単位(0.5日)の取得か」についても把握できるように記載しましょう。
③「基準日」:労働者に年次有給休暇を付与した日
労働基準法では、6ヵ月経過日とその日から起算した継続勤務年数1年ごとに付与日(基準日)が発生することになります。
労働基準法で定める基準日よりも前倒しで付与する場合(例えば、4月1日入社の新入社員に入社と同時に10日間の年次有給休暇を与えるケース)には、前倒しして付与した日を「基準日」として記載します。10日間のうち、一部を労働基準法で定める基準日より前倒しで付与(分割付与)した場合は、付与日数の合計が10日に達した日が基準日となります。
【POINT】年次有給休暇管理簿の指定様式はある?
年次有給休暇管理簿に決まった書式はないため、記載しなければならない事項が記載してあれば、労働者名簿や賃金台帳とあわせて調製してもかまいません。また、いつでも出力できるような仕組みであれば、システム上で管理できます。また「厚生労働省(福井労働局)のホームページ」に年次有給休暇管理のフォーマット様式のサンプルがありますので、ぜひ参考にしてください。
年次有給休暇管理簿の管理方法

年次有給休暇管理簿の管理方法はさまざまあり、それぞれにメリットとデメリットを紹介します。自社にあった管理方法を選びましょう。
紙
手書きで作成しても問題ないため、紙による管理が可能です。システムやネットワークの影響を受けず、ITに不慣れな方にも使いやすいのが、紙ベースの管理方法です。最も導入しやすく、メモが自由にでき、コストもほとんどかかりません。しかし、保管するスペースが必要になるため、他の書類に埋もれて探すのに手間がかかることがあります。
紛失リスクもあり、ファイルなどできちんと管理しなければなりません。さらに、次年度へ繰り越す場合など転記に時間がかかることは、デメリットといえるでしょう。
エクセル
エクセルならパソコンが1台あれば導入は簡単です。データで保管することができるので紙で出力する必要もありません。すでに、パソコンがある場合はコストもほとんどかかりません。
しかし、関数を利用して数式を組む場合、慣れていないと誤って数式を消してしまう可能性があります。また、従業員が増えると管理が煩雑になり、手間がかかることもデメリットです。
さらに、パスワードを設定してセキュリティ対策を施さないと書き換えられてしまう危険性もあります。
システム
勤怠管理システムを利用すれば、自動で年次有給休暇の付与、取得日、残数の管理が可能です。特にクラウド型のシステムの場合、インターネット環境が整っていればいつでも出力でき、法改正があった場合でもシステム提供会社側でバージョンアップに対応していることが多く、実務のフロー変更にもスムーズに対応できるでしょう。
次年度へ繰り越すときにも転記ミスはなく、書き間違えのリスクもありません。ただし、コスト面や、自社独自の管理簿にカスタマイズがしにくい点はデメリットです。
総合的には、担当者の煩雑な管理の悩みを大きく減らせる点が大きなメリットになるため、システムでの管理をおすすめします。
勤怠管理システムで年次有給休暇管理簿を作成
年次有給休暇は、採用日によって付与日や時効消滅する日が異なります。通年採用を行っている企業であれば、有給休暇の付与日が複数存在していることが多く、管理が行き届かずに結果的に法令違反となってしまう恐れがあります。そこで、勤怠管理システムを活用すれば年5日の取得義務に対する年次有給休暇管理を自動化し、エクセルや手書きよりも大幅に時間を節約できるようになります。特にシステムを使うことのメリットとして、単に対象者の取得状況を管理できるだけでなく、休暇取得の呼びかけ(アラート機能等によって)を行うことができるなど、リマインド機能を兼ね備えている強みもあります。取得時季の期限が年度末等で繁忙期と重なる場合、取得の呼びかけによって法令違反を回避できるのであれば大きなメリットと言えるでしょう。
そのほかにも勤怠管理システムで年次有給休暇管理簿を作成するメリットがあります。たとえば、年10日以上の有給付与対象者に対して自動で有給休暇管理簿が作成されるため、ことから対象者を見落としリスクの防止につながります。また、取得日数をシステム内で自動的に集計・管理しているため、いつでも手軽に取得状況を把握することができるようになり、管理者側の負担を軽減することができます。
まとめ
労働基準法の改正前は管理方法についての定めはなく、企業独自の管理方法で行われていました。しかし、働き方改革関連法が成立し、労働基準法が施行された2019年4月から年10日以上年次有給休暇が付与される従業員に年5日の年次有給休暇を取得させることは企業の義務となり、年次有給休暇管理簿についても使用者に作成と保存が義務付けられています。
適切かつ効率的に年次有給休暇管理簿を作成・運用し、従業員が年次有給休暇を確実に取得できるように管理方法を見直してみましょう。
メールで受け取る

働き方改革関連法へ対応!勤怠管理システム「楽楽勤怠」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
- 監修蓑田 真吾
- 社会保険労務士
1984年生まれ。社労士独立後は労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は様々な労務管理手法を積極的に取り入れ労務業務をサポートしています。また、年金・医療保険に関する問題や労働法・働き方改革に関する実務相談を多く取り扱い、書籍や雑誌への寄稿を通して、多方面で講演・執筆活動を行っている。
https://www.minodashahorou.com/
こんなお悩みありませんか?
そのお悩み で解決できます!
で解決できます!

実際のシステム画面をお見せしながら
現在の運用方法についてお伺いし、
貴社に合わせた運用提案を
させていただきます。
ご要望に合わせてWEBでのご案内も可能です。
知りたい方はこちら

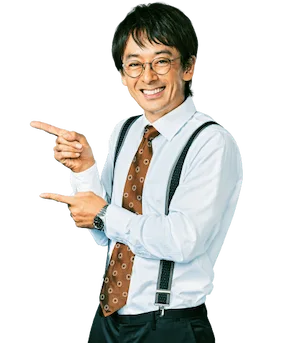
 とは
とは
「楽楽勤怠」は勤怠管理・給与計算を
ラクにするクラウド型のシステムです。
- 従業員
- 従業員ごとに用意されたアカウントにログインし、打刻や勤怠申請を行います。
- 「楽楽勤怠」
- 勤怠情報をシステムで一元管理し、給与計算に必要なデータを自動集計します。
- 人事労務担当者
- システムからデータ出力して給与システムに連携するだけで簡単に給与計算を行うことができます。
出退勤や残業、休暇取得などの勤怠情報を一元管理し、給与計算に必要なデータを1クリックで出力します。
インターネットに接続可能なパソコンやスマートフォンがあれば外出時や在宅ワーク時にも利用可能です。
あなたの会社の働き方改革に貢献する勤怠管理システムです。
「楽楽勤怠」が
選ばれている理由

豊富な機能群
現状運用にあわせた課題解決や業務効率化を実現します。

初めても乗り換えも安心の、
専任サポート
※2024年3月末現在
ご要望に合わせてWEBでのご案内も可能です。
知りたい方はこちら

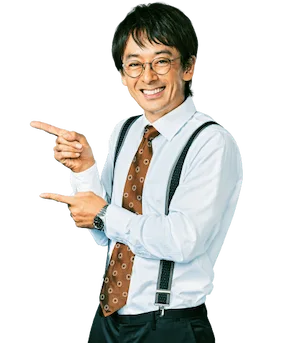
関連サービスのご紹介
「楽楽勤怠」の姉妹製品・関連サービスのご紹介です。
バックオフィス業務のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ83,000社以上のご契約をいただいています(※2024年3月末現在)。「楽楽勤怠」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。
「楽楽勤怠 クラウドサービス」は「IT導入補助金2024」の対象ツール(通常枠のみ)です。
補助金を受けるためには、導入契約を締結する前にIT導入補助金事務局(事務局URL:https://it-shien.smrj.go.jp/)に対して交付申請を行う必要がありますので、その点に留意してください。
なお、補助金の交付を受けるには所定の要件を満たす必要があります。
※現在は申請期間外となります。


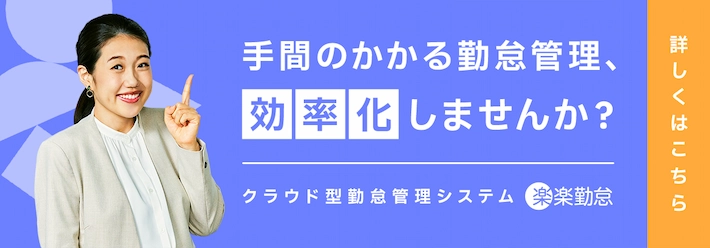
 とは
とは




