建設業向けの勤怠管理システムとは?機能や導入メリットから選び方まで解説

2019年4月から順次施行されている働き方改革関連法は、労働環境にさまざまな影響を及ぼしています。建設業においては、2024年4月1日より労働時間の上限規制が適用開始されたことで、働き方にさらなる変革が求められています。
しかし、建設業界では労働時間の面以外にも、多様な勤務形態や頻繁なスケジュール変動により、勤怠管理においての課題が山積みとなっている企業が存在する状況です。また、法改正への対応に苦慮している企業も少なくないのではないでしょうか。
建設業界ならではの複雑な勤怠管理の効率化には、多様な打刻方法や工数管理などの機能を備える勤怠管理システムの導入がおすすめです。
本記事では、建設業界向けの勤怠管理システムについて、建設会社の課題解決のために活用すべき機能や導入メリットをご紹介します。また、どういったシステムなら業務の効率化と生産性の向上が図れるのかについて具体例を示しながら解説していきます。
勤怠管理システム導入を検討する際の参考にしていただき、そのメリットをぜひ実感してください。
※(参考)厚生労働省「働き方改革関連法に関するハンドブック」
この記事の目次
建設業界で勤怠管理が重要視される理由
建設業界で勤怠管理が重要視される理由は、業界ならではの複雑な労働環境や勤務体制においても従業員の勤務状況を適切に管理することが求められているからです。ほかの業界と違い、建設業では事業の性質上、次のようなさまざまな労働環境が混在しています。
- プロジェクトごとに勤務場所が異なる
- 現場に直行直帰する従業員が多い
- 出入りする労働者には多様な職種・勤務形態の人がいる
そのため、従業員ごとの労務管理や労働時間をきめ細やかに把握することが困難です。ほかにも作業が天候に左右されたり、近年では猛暑日の増加によって思うように業務がはかどらなかったりするケースも増えてきました。自然災害が起これば復旧工事が優先される場合もあり、特別な事情により工期が大幅に遅れてしまったり、予定どおり進まない事態が起こったりするることもしばしばみられます。その結果、他業種よりも時間外労働が増える傾向にあるのは事実です。
また、仕事に関わっている人の多さと、それに伴う人件費の管理や多岐にわたる工数マネジメントなど、オフィスワークの負担も小さくありません。このような現状が考慮され、働き方改革に伴う労働基準法の改正によって設けられた時間外労働の上限規制は、運送業や医師と同様に建設業界にも適用が猶予され、2019年から5年間の準備期間が与えられていました。
しかしそればかりでなく、労働者の確保や給与・社会保険の充実、生産性の向上など建設業界における課題はもとより山積しており、適切な勤怠管理を行うためのシステム構築をはじめとした業界全体の改革が急務とされているのです。
以下では、建設業界で勤怠管理が重要視される理由を具体的に解説します。
※(参考)国土交通省「建設業の働き方として目指していくべき方向性」
使用者は勤怠管理を行う義務を負うため
2019年4月に施行された労働安全衛生法の改正により、使用者には「客観的な記録による労働時間の把握」が法的義務となりました(※)。
対象となるのはすべての従業員の勤務時間および時間外労働で、タイムカードによる記録やパーソナルコンピューター等の電子計算機の使用時間など、客観的な方法で記録することが義務付けられています。
また、使用者は把握した労働時間の記録を3年間保存するための必要な措置を講じる必要があり、退職したからといって破棄することなどはできません。
※(参照)出雲労働基準監督署「客観的な記録による労働時間の把握が法的義務になりました」
建設業の2024年問題への対応が求められているため
長時間労働が常態化していた建設業界において、ワークライフバランスの推進は重要視されています。
労働環境を改善すれば、深刻な問題となっている人手不足の解消にもつながるためです。
そこで、これまで適用が猶予されてきた改正労働基準法に基づく時間外労働の上限規制(原則として月45時間、年360時間を限度時間とする)の遵守が2024年4月より義務付けられています。特別条項も規定されていますが、違反した場合は罰則もあり、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金となっています。
とはいえ、人件費や資材が高騰するなかで、労務管理の整備ともなれば事業者の負担は大きいことが考えられます。こうした課題が複数存在する状況が、がいわゆる建設業界における“2024年問題”といわれているのです。
※(参照)厚生労働省「労働基準法における労働時間の定め」「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」
建設業の勤怠管理における課題
建設業界には、特殊な業態ゆえの多くの課題がひそんでいます。
独特な労働環境が常態化しており、改革したいと考えていても、従来からのやり方の変更には大きな障壁を感じるのではないでしょうか。まずは勤怠管理を複雑化させている要因をきちんと把握することが解決の糸口です。
以下では、勤怠管理における建設業界での主な課題を紹介します。問題点を一つひとつしっかり洗い出し、整理するところから始めていきましょう。
不正打刻の懸念がある
不正打刻の懸念は、建設業界の勤怠管理における大きな課題のひとつです。
建設業界では、現場への直行直帰が多くなりがちです。そのため、始業から終業まで、労働者がどこでどのように業務を行っていたのか正確に把握することが難しくなっています。たとえ、現場にタイムレコーダーがあったとしても、同僚など第三者に打刻させるといった不正が発生する恐れがあります。ましてや、手書きによる日報への記録や電話連絡の場合、その正確性には疑問が残ります。
勤務状況の記録・残業時間の管理が難しい
建設業界では日々の業務に追われることで、あとからまとめて勤務状況を記録したり、個別に正確な残業時間を残せなかったりと、勤務状況の記録・残業時間の管理が困難になっています。
とりわけ勤怠管理をタイムカード打刻やExcel管理などで行っているような場合は集計に手間がかかるだけでなく、手作業による記録ミスが発生する可能性があり、確認作業にも大変な労力が必要になってきます。
シフト管理に手間がかかる
建設業界の場合、作業シフトなどはかなり複雑化し、シフトの管理や作成に相当な手間がかかります。というのも建設現場など勤務場所だけでなく、勤務時間も状況に応じて変動することが往々にしてあるからです。
そこに正社員だけでなく、派遣社員やパート・日雇いの労働者などが含まれてくると、それぞれの雇用条件に合わせた勤務時間の調整と管理や給与の支払いが生じ、管理者の負担は増大するばかりです。
業務効率の向上を検討する際、Excelでの管理に限界を感じている企業も少なくないのではないでしょうか。
勤怠管理をリアルタイムで行いづらい
多くの作業工程を管理しながら、それぞれの現場ごとの労働者の勤怠状況をリアルタイムに把握することは困難を極めます。
とはいえ、法律に沿った労働時間の管理と把握を実施するには、確認したいそのときに誰がどのくらい働いているのかを知る必要があります。
タイムカードなど紙の打刻による勤怠管理におけるデメリットの一つが、リアルタイムの勤怠確認ができないことにあるように、月途中での時間外労働超過を防ぐための対策も含めて確実に勤怠管理を行う対策が必須といえます。
勤怠報告(日報)の信ぴょう性・客観性が乏しい
自己申告による勤怠管理では、記載漏れや転記ミスが起こりやすいだけでなく、信ぴょう性も劣ります。
しかし、建設現場の環境によっては、タイムレコーダーを設置できないこともあるでしょう。その場合、日報に記録して勤怠管理を行っているケースもまま見受けられます。
そのため、労働安全衛生法に規定されている「客観的な記録による労働時間の把握」ができなくなってしまいます。
勤怠と工数の並行管理が煩わしい
工程数の多さだけでなく、建設業には工期という大きな縛りもあります。
そうしたなか、適切な人員の配置やシフト管理を行っていくのは容易なことではありません。ただでさえ変則的な業務において、それらを並行管理する労務担当者の負担は大きく、小さなミスの積み重ねが大きなトラブルにつながっていく可能性も低くはないでしょう。
業務の効率化を図るうえでも、できるだけ煩わしい作業が発生しない勤怠管理のシステム構築が不可欠です。
建設業が勤怠管理システムを導入することのメリット
建設業界特有の悩みを解決することはもちろん、法改正への対応についても一気に解決するためには、やはり建設業向けの機能を備えた勤怠管理システムを導入することがおすすめです。
ここでは、前章までに挙げた課題に基づき、勤怠管理システムを導入することで何が解決するのか、そのメリットなどについて解説します。
複雑な勤務体系の勤怠管理が可能になる
勤怠管理システムであれば、シフト制・フレックス制などの様々な労働時間制のほか、直行直帰や個々の雇用条件が複雑化しやすい建設業界におけるさまざまな勤務体系に対応可能です。
建設業界では、それぞれの従業員が担当するプロジェクトに応じて勤務場所や勤務時間が異なるため、従来のタイムカード管理やExcelによる集計では勤怠管理がかなり困難となるケースが多く発生してしまいます。
こうした複雑な勤務体系における勤怠管理のネックに対して、従業員ごとの働き方をシステム上で自動的に集計・管理できることは、勤怠管理システム導入の大きなメリットでしょう。
労働時間をリアルタイムで正確に把握できる
従業員の出退勤や労働時間を勤怠管理システムで一括管理すれば、そのデータはクラウド上に保存されるので、誰がどのくらい働いているのか、いつでもどこでもリアルタイムに把握することができるようになります。
また、月内の残業時間が超過したときも、アラーム機能によって月末の集計まで待たずに通知されるので、オーバーワークの防止につながります。
勤怠管理システムの活用で従業員の労働時間をリアルタイムで可視化できるようになれば、人事労務担当者だけでなく、従業員自身の法令遵守や健康管理への意識向上にも寄与するでしょう。
不正打刻が防止できる
建設業界における勤怠管理の課題としてよくみられる不正打刻のリスクに関しても、システム管理であれば軽減できるでしょう。
不正打刻で多いのは、実際は本人が不在であるにも関わらず、同僚などに代理打刻をしてもらうといったようなケースです。
勤怠管理システムはGPSで位置情報を取得できたり、顔認証で打刻を行えたりするので、本人以外の打刻が困難となります。
また勤怠管理システムを導入した場合、多くのサービスはスマートフォンやタブレットでの打刻に対応しているので、異なる現場においてもスムーズに打刻が可能です。
不正打刻を防ぎつつ、打刻の正確性も向上できる部分は、紙やExcelでの勤怠管理と比較した場合の大きなメリットだといえます。
シフト管理業務を効率化できる
勤怠管理システムならば、手作業によるシフトづくりに比べてミスを減らすことができ、管理業務の負担も小さくなります。
勤怠管理システムの多くは、シフト表を作成できる機能が備わっています。また、勤務実績が自動で照合できるため、管理業務を大幅に軽減可能です。
時給や日給・残業など、雇用条件や細かなスケジュールに対応したシフト作成も可能なため、これまでEXCELで行っていたような煩雑な作業は不要となり、シフト管理業務の効率化につながります。
工数管理が同時にできる
勤怠管理だけでなく、建設業界で重要な工数管理も同時にできる部分は、勤怠管理システムのメリットです。
建設業向けの勤怠管理システムには、オプションで工数管理機能を追加できるものがあります。工数データを自動集計し、タスクごとにデータ分析やグラフ化などをすることで、稼働状況の可視化も可能です。
従業員の勤怠情報を確認しながら、プロジェクトの進行具合も管理できるので、生産性の向上につながります。
各種の法改正に対応している
勤怠管理システムは、労働基準法など各種労働関連の法改正に対応し、自動アップデートできることも大きな強みです。
特に複雑な勤怠管理が求められる建設業では、常に最新の法改正にアップデートしてくれるシステムであることが求められます。
時間外労働のルール変更や、残業代の計算方法など、法改正により変更となる部分に自動で対応してくれるサービスがあれば安心です。
建設業界向け勤怠管理システムの選定ポイント
建設会社が勤怠管理システムを選ぶ際には、自社の環境と従業員の勤怠状況に適した打刻方法に対応しているシステムを選びましょう。
たとえば、従業員にとって現場への直行直帰やリモートワークが多い環境であるならば、社外でも通用する打刻方法を備えたシステムが必要といったことなどです。
以下では、建設業界向けの勤怠管理システムの選定ポイントについて紹介していきます。
スマートフォンやタブレットでの打刻に対応しているか
建設会社が勤怠管理システムを選ぶ際には、パソコンや固定の打刻機器だけでなく、スマートフォンやタブレットなどの場所を問わずに打刻できる仕組みかどうかを確認しましょう。建設業界の労働環境としては、どうしても現場への直行直帰が多くなりがちです。そのためスマートフォンやタブレットなどを用い、ネットを通じてログインや出退勤の打刻が社外で行えるシステムを採用することは必須といえます。
その際にGPS機能などが備わっていれば、不正打刻の防止により大きな強みを発揮するでしょう。
従業員にとって操作しやすいか
パソコンやスマートフォンでの操作に慣れていなくても操作しやすいかといったように、従業員にとっての操作性に関しても配慮が必要です。
できるだけ入力負担が少なく、操作性のよい製品を選ぶためには、導入前に無料トライアルなどを活用する方法もあります。導入後もITリテラシー向上を支援する勉強会の実施や、システム自体のサポート体制が充実したものを選ぶようにしましょう。
残業時間・有休取得時状況などを可視化できるか
残業時間や有給休暇の取得状況などをシステムの活用により可視化することで、従業員の勤怠状況を素早く確認できます。
月内の残業時間が超過した従業員には、アラート機能によって自動通知し、オーバーワークを防止することも可能です。誰がどのくらい働いているのかを知りたいときに、リアルタイムに把握できるようになることで、人事労務担当者の作業負担は大きく軽減できるのではないでしょうか。
工数管理など業界特有の必要とされる機能を追加できるか
工数管理は、建設業務の作業進行において重要な要素です。現場ごとに異なる工数はもちろん、シフト作成や原価管理など、建設会社でのさまざまな状況に必要とされる機能がシステムに備わっているか、または追加できるかどうかを確認しましょう。
あらかじめ工数管理機能が搭載されている製品もありますが、オプションや外部システムとの連携により自社の特徴に合わせてカスタマイズできるような場合もあります。
システムを導入することで本当に業務効率を上げられるのか、事前によく確認しておきましょう。
申請・承認機能が備わっているか
建設会社で勤怠管理システムを選ぶ際は、申請・承認機能が備わっているかを確認しましょう。
建設業のような現場優先の業態では時間外労働(残業)が発生する場面も多くあります。急遽時間外労働が生じた場合の申請・承認はもちろん、有給休暇や法定休日の取得状況などが一括して見える化できる点は、勤怠管理システムの大きなメリットです。さらにデータはクラウド上で管理されるので、紙の記録によるやり取りがなくなる分、労務担当者の負担も軽減でき、スムーズな申請・承認が可能になります。
建設業の勤怠管理をクラウド型システム「楽楽勤怠」で効率化しよう
勤怠管理システムは、従業員の勤怠データの管理を自動化するだけでなく、労働時間のリアルタイム集計や打刻ミスの防止、複雑な法改正への対応などメリットが数多くあります。
特に建設業界において課題とされている、「さまざまな勤務場所」「勤務時間の混在」「シフトや雇用形態の多様性」「マネジメントすべき工数の多さ」などを網羅しながら適切に管理するには、勤怠管理システムの導入が大きなメリットとなることでしょう。
株式会社ラクスが提供しているクラウド型の勤怠管理システム「楽楽勤怠」は、出退勤や残業、休暇の取得状況など、勤怠データを一元的に管理することができます。また、業界や企業ごとの独自ルールや法律に対応する機能が豊富で、もちろん建設業界特有の勤怠状況にも対応しています。さらに専任サポート体制で、運用前から安心のサポートが受けられることも「楽楽勤怠」の特長の一つです。
企業ごとに合わせて柔軟にな運用方法を提案いたしますので、勤怠管理システム導入を検討される際には、ぜひお気軽にお問い合わせください。
メールで受け取る

働き方改革関連法へ対応!勤怠管理システム「楽楽勤怠」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
- 監修楽楽勤怠コラム編集部
- 「楽楽勤怠」コラム編集部です。
人事労務担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報をお届けしています。
https://www.rakurakukintai.jp/
こんなお悩みありませんか?
そのお悩み で解決できます!
で解決できます!

実際のシステム画面をお見せしながら
現在の運用方法についてお伺いし、
貴社に合わせた運用提案を
させていただきます。
ご要望に合わせてWEBでのご案内も可能です。
知りたい方はこちら

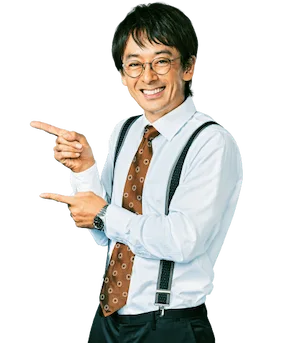
 とは
とは
「楽楽勤怠」は勤怠管理・給与計算を
ラクにするクラウド型のシステムです。
- 従業員
- 従業員ごとに用意されたアカウントにログインし、打刻や勤怠申請を行います。
- 「楽楽勤怠」
- 勤怠情報をシステムで一元管理し、給与計算に必要なデータを自動集計します。
- 人事労務担当者
- システムからデータ出力して給与システムに連携するだけで簡単に給与計算を行うことができます。
出退勤や残業、休暇取得などの勤怠情報を一元管理し、給与計算に必要なデータを1クリックで出力します。
インターネットに接続可能なパソコンやスマートフォンがあれば外出時や在宅ワーク時にも利用可能です。
あなたの会社の働き方改革に貢献する勤怠管理システムです。
「楽楽勤怠」が
選ばれている理由

豊富な機能群
現状運用にあわせた課題解決や業務効率化を実現します。

初めても乗り換えも安心の、
専任サポート
※2024年3月末現在
ご要望に合わせてWEBでのご案内も可能です。
知りたい方はこちら

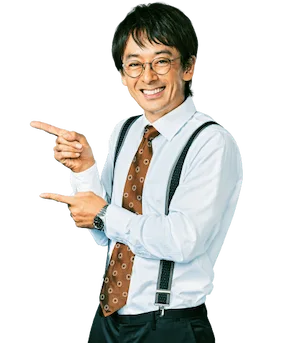
関連サービスのご紹介
「楽楽勤怠」の姉妹製品・関連サービスのご紹介です。
バックオフィス業務のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ83,000社以上のご契約をいただいています(※2024年3月末現在)。「楽楽勤怠」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。
「楽楽勤怠 クラウドサービス」は「IT導入補助金2024」の対象ツール(通常枠のみ)です。
補助金を受けるためには、導入契約を締結する前にIT導入補助金事務局(事務局URL:https://it-shien.smrj.go.jp/)に対して交付申請を行う必要がありますので、その点に留意してください。
なお、補助金の交付を受けるには所定の要件を満たす必要があります。
※現在は申請期間外となります。


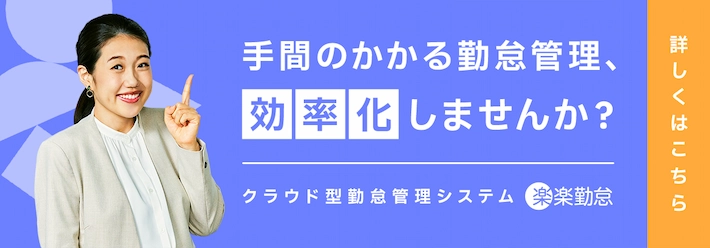
 とは
とは




