中小企業向けの勤怠管理システムで業務を効率化!導入メリットや選び方を解説

働き方改革の進展やコンプライアンス意識の高まりなどを背景に、勤怠管理システムを導入している、あるいは導入を検討している企業が増えています。一方、数ある勤怠管理システムのうち、自社に最も適したシステムをどのように選んだらよいかわからないと感じている人事労務担当者も多いのではないでしょうか。
特に中小企業では、導入・運用にかかる手間とコストが障壁となり、導入に二の足を踏んでいるケースも見受けられます。しかし、勤怠管理システムは、労務管理の効率化や法令改正への対応において非常に大きな効果が期待できるツールです。
本記事では、中小企業における勤怠管理システムの導入がもたらすメリットや導入時のポイントについて解説します。
この記事の目次
勤怠管理における中小企業ならではの課題
2017年1月20日に厚生労働省が策定した労働時間の適正な把握のためのガイドライン(※)では、従業員の労働時間を「客観的な記録」により適正に把握する責務があることが示されました。
しかし、長年手書きの勤務表やタイムカード管理を行ってきたものの、これまでのやり方のままで適正な勤怠管理ができるのかと不安を抱える中小企業も見受けられます。また、勤怠管理システムを導入してはみたものの結局使いこなせていなかったり、自社のやり方にマッチせず、一部Exceなどを用いた手計算で管理をしていたりするケースもあるでしょう。
こうした手動の作業が入ることで、集計ミスなどのエラーに加え、不正打刻の問題が発生するリスクもぬぐえません。
この章では、まず中小企業ならではの勤怠管理の課題について探っていきます。
※(参考)厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
勤怠データの集計に手間と時間がかかる
従業員の勤怠データを手作業で入力して集計するとなると、膨大な時間と手間がかかってしまいます。また、データを転記する際にミスが発生しないとも限りません。さらに、システムによってある程度集計できていたとしても、残業や休日出勤・有給休暇の管理など勤怠管理システム自体が自社の仕組みにマッチしていなければ、どこかに手作業が発生する場面も出てきます。
こうした作業は毎月の締め日ごとに発生するため、作業工数が膨れ上がり、「締め日になるといつも残業ばかりで大変」というお悩みを抱える人事労務担当者も多いでしょう。
従業員ごとの勤務状況が把握しにくい
従業員ごとの働き方が多様であればあるほど、勤務時間や休憩時間などの勤務状況が把握しにくく、集計も煩雑になりがちです。
とはいえ中小企業では、需要の変動や繁閑差への対応として勤務時間が変動しがちであったり、正社員やパート・アルバイトなど、従業員の雇用状況によって勤務時間や出社日がまちまちになっていたりするるケースはよくあることです。また、テレワークを導入している会社の場合、在宅における従業員の勤務時間の把握も勤怠管理の大きなな課題といえます。
法改正への素早い対応が困難
手作業による従来のアナログ的な勤怠管理では、労働基準法が改正された際など素早い対応が困難な場合があります。
たとえば働き方改革の一環として、2023年4月1日より、これまで大企業ではすでに適用されていた月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用されるようになりました。(※)
このように労働基準法などで働き方に関する条文が改正・施行されると、勤怠管理における実務も、それに即した内容に速やかに変更していかなければなりません。
※(参考)厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
業務が特定の担当者に集中し属人化してしまう
勤怠管理を紙のタイムカードやExcelなどのアナログ管理で行っている場合、業務が特定の担当者に集中し、「属人化してしまう」というのも中小企業にありがちなケースです。
しかし、毎月の勤怠締めの管理から給与計算までを人事・総務担当の特定の従業員が行っているのは中小企業でよく見られることです。中には人事・総務以外の、いわゆるバックオフィス機能をすべて担っているようなこともあるのではないでしょうか。
このような体制では、業務のブラックボックス化や、業務量過多による従業員の退職などにつながりかねません。
人為的ミスや不正打刻のリスクがある
あってはならないことですが、手書きの勤務票や紙のタイムカードの打刻によって勤怠管理を行っているケースでは、どうしても不正打刻が起こり得てしまいます。
たとえば、「遅刻しそうだから先に出勤している従業員に頼んで打刻してもらう」のように、本人でない者による打刻ができてしまうなどのリスクです。
また、不正が行われずに正しく打刻されていたとしても、その後の集計を手作業で行っているような環境下では、ミスの発生をゼロにするのは困難といえます。
中小企業ですでに勤怠管理システムを導入しているような場合でも、作業フローの一部でシステム以外に人の手を介在する工程があったとすれば、勤怠管理のミスを100%なくすのはやはり難しいのではないでしょうか。
中小企業向け勤怠管理システムのメリットを管理者・従業員の視点で解説
前項で解説したように、中小企業の勤怠管理にはさまざまな課題が存在します。
中小企業向けの勤怠管理システムを導入すると、これらの課題がどのように解決されるのでしょうか。労働基準法(※1)や労働安全衛生法(※2)にて規定されている法令を参考に、管理者側・従業員側の視点でそれぞれを見ていきましょう。
- (※1)参考:「労働安全衛生法第66条8の3」
- (※2)参考:「労働基準法第109条」
管理者に対するメリット
まずはじめに、勤怠管理システムの導入による管理者視点でのメリットを解説します。
自社の人事労務担当者が行っている勤怠管理業務をイメージしながら、勤怠管理システムがどのように役立つのかを確認していきましょう。
勤怠データ集計が自動化し、業務効率化につながる
勤怠管理システムを活用すれば、さまざまな雇用形態で働く従業員の勤務状況を一括し、システム上で管理することができます。
たとえば、パートやアルバイトなどの煩雑なシフト作成や調整もシステム上で行うことが可能です。また、すべての従業員の勤怠データを自動で集計し給与計算に必要なデータの作成が簡単になるため、勤怠時間の計算にかかっていた工数を一気に削減することもできるでしょう。
勤怠管理システムの導入により、業務を圧倒的に効率化できることは管理者にとっての大きなメリットだといえます。
従業員による不正打刻リスクを軽減できる
勤怠管理システムには以下のような技術で不正打刻を防止する仕組みを備えているため、従業員による不正打刻のリスクを大幅に軽減できます。
- 生体認証
- 位置情報やPCログでの在籍確認
- クラウド管理によるデータ改ざん防止
紙のタイムカードやExcelで打刻を行っている場合は、打刻時間を編集したり、第三者が代理打刻したりする不正を防ぎきることは難しいでしょう。
しかし、勤怠管理システムで打刻を行うことで、勤務データ記録の正確性が大幅に向上するため、不正打刻防止や企業の労務管理の信頼性を向上させることができます。
法改正への対応が迅速に行える
勤怠管理システムであれば、法改正に際して自動アップデートが行われるので、その項目を手動で再設定する必要がありません。
例えば、割増賃金率の変更や時間外労働の上限規制などが改正された場合、最新の規則に基づく集計が可能です。
昨今の働き方改革関連法の対応にあたり、長時間労働を抑制するための適切な勤怠時間の把握が大前提となっています。勤怠管理システムを活用することで、残業や休日出勤の時間はもちろん、有給休暇の取得状況などを従業員ごとに簡単に管理することができます。また、残業が多い従業員にアラートを出すなど、長時間労働を抑制する仕組みを通じて法令への対応が可能です。
人件費を中心とするコスト削減が可能
勤怠管理システムにより、従業員ごとの勤怠データを自動集計して給与計算に活用することができます。
給与計算に必要な勤怠データの集計のために、毎月の勤怠締めに膨大な工数と人件費をかけて実施していた勤怠管理の時間とコストを大幅に削減できます。また、すでに勤怠管理システムを導入している中小企業でも、手計算などで対応している箇所があるとすればそこに時間やコストがかかっているはずです。
しかし、自社の運用にマッチするシステムへの切り替えによって一連の集計作業を自動化してしまえば、その時間や費用も削減可能です。
就業状況の分析で人事戦略に活用できる
勤怠管理システムの活用により就業状況を正確に把握し分析することで、効果的な人事戦略の考案に役立ちます。
勤怠管理システム上では、従業員の勤怠状況を一括、かつリアルタイムに把握できるので、どの部門・どの従業員が長時間労働の傾向にあるかなどを可視化できます。システム上で長時間労働に結び付いている原因を洗い出すことで、人員を再配置する・研修を実施するなどの効果的な施策考案に役立つでしょう。
このように、積極的な人事戦略に勤怠管理システムを活用することもできます。
特定の担当者にかかる過度な勤怠管理業務負担を解消できる
特定の担当者や部署に勤怠管理の負荷が集中してしまうような状況は、システムによって業務を自動化することで解消されます。
中小企業では、社内事務や管理業務などのバックオフィス機能において、一時期に特定の担当者に負荷が集中してしまうことが見受けられます。特に勤怠の締めの時期に、担当部署に過度な業務負荷がかかってくることも珍しくありません。すると、その担当者に何かあったときなど、たちまち業務が遅延してしまうようなことも起きかねないでしょう。
このような属人化のリスクを回避するためには、勤怠管理システムによって業務を自動化し、手動での作業を極力減らしていくことがポイントです。
従業員に対するメリット
続いて、勤怠管理システム導入による従業員視点でのメリットを紹介します。
勤怠管理の管理者である人事労務担当者におけるメリットだけでなく、従業員にとってもメリットとなるポイントがあることで、自社でのシステム導入がよりスムーズになるはずです。従業員の業務効率化にもつながるかをイメージしながら、それぞれのメリットを確認していきましょう。
直行直帰・リモートワークでも打刻が簡単
勤怠管理システムであれば、外出先でもスマートフォンから打刻できたり、リモートワークでも打刻できたりするなど、働く場所を問わず打刻が可能です。
一方、旧来の紙のタイムカードなどを用いた勤怠管理の場合、出社しないと打刻ができません。また、直帰したいのに打刻できないことから一旦帰社し、打刻を済ませて帰宅するといったケースもあるでしょう。
勤怠管理システムを導入すれば、直行・直帰などの働き方における打刻へ柔軟に対応できるようになり、従業員にとっては働く意欲の向上にもつながるでしょう。
休暇申請をシステム上でスムーズに行うことができる
勤怠管理システムならば、休暇の申請から承認までの一連の作業をシステム上で行うことが可能です。また、申請された内容がシステム上で一括管理されるので、いつどんな内容で申請したかが従業員もすぐにわかります。
従業員が有給休暇を取得したい場合、これまでは上長に申請用紙を提出するのが一般的なスタイルでした。現在も、そのような運用をしている中小企業は多いのではないでしょうか。
しかし、勤怠管理システムであれば働く場所や時間を問わずに申請でき、なおかつ休暇の取得状況が把握しやすくなるという点も従業員側のメリットです。
中小企業が勤怠管理システムを選ぶ際のチェックポイント
中小企業の人事労務担当者が勤怠管理システムを導入しようと考えたとき、どのようなポイントに気を付ければよいのでしょうか。
勤怠管理システムにはさまざまな機能が備わっています。自社にとってどんな機能が必要なのか、項目ごとに見るべきポイントを解説していきます。
自社の勤務形態に合っているか
まず、自社の勤務形態に合っているかどうかが重要なポイントです。企業によって、従業員の勤務形態は多岐にわたります。
勤怠管理システムは製品ごとに打刻方法やシフト管理などの機能が異なるため、「正社員が多いのか?」「シフト制のパート・アルバイトが多いのか?」「裁量労働制で働く従業員はいるのか?」など、自社の勤務形態に適したシステムを選びましょう。
たとえば社外で働く従業員が多いのであれば、外出先で打刻できるような仕組みがあるのかなどがポイントとなります。
また、シフトが複雑な非正規雇用が多いのであれば、シフトの作成・調整機能はあるのかどうかも事前に確認しておきましょう。
就業規則に沿ったカスタマイズが可能か
システムが自社の就業規則に適しているのかどうかも重要な選定ポイントです。
休暇制度や割増賃金額など自社独自のルールを設定している場合、勤怠管理システムを自社ルールに沿ってカスタマイズできるかどうかをしっかりチェックしましょう。
自社のルールに適合しない部分を残したまま導入し運用を始めてしまうと、非適合の部分は結局手作業によって補わなくてはならず、非効率です。これではシステムを導入する意味もありません。
自社の就業規則に沿ったカスタマイズが可能なのかどうかの確認は、妥協しないことが重要です。
給与計算ソフトなど人事システムとの連携性はどうか
給与計算で導入しているソフトや、その他の会計ソフトなどとの連携性に問題がないかどうかも、勤怠管理システム選びにおいて重要なポイントです。
せっかくシステムを導入しても、勤怠管理データを給与計算ソフトに渡す際に連携が不十分であったとすれば、手作業など余計な工数がかかってミスの発生リスクが付きまといます。また、すでにシステムを導入しているものの他ソフトとの互換性や連携性に課題を感じているような場合も、改めてスムーズに連携できるシステムへの切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。
法改正への素早いアップデートが可能か
法改正の施行タイミングで、アップデートした内容が反映されるかどうかも大事なチェックポイントです。
随時行われる労働法関連の法改正は、給与の支払いなどに影響のある重要な項目が多く、対応していないと法律違反を犯してしまう危険があります。手動で運用を変更するには工数も多く、さまざまなバックオフィス業務を抱える中小企業の担当者にとって大きな労務負担となります。
勤怠管理システムの機能で法改正へのスムーズな対応がクリアできれば、格段に工数・時間削減の効果が上がることでしょう。
セキュリティ機能やサポート体制が備わっているか
安全で信頼できる勤怠管理システムを選ぶには、セキュリティ対策やサポート体制が充実しているかどうかも重要なチェックポイントです。
これまでアナログな手法で勤怠管理を行ってきた企業の場合、担当者が勤怠管理システムに不慣れなことは仕方がありません。そのような場合、システムを提供する業者のサポート体制に頼ることになります。
セキュリティ対策やサポートサービスの種類は製品よってまちまちですが、以下のポイントでの見比べがおすすめです。
| セキュリティ面 | サポート面 |
| 暗号化やセキュリティ認証などのデータ保護対策が可能か | 導入時にオンラインや電話のサポートが受けられるか |
| 権限管理などのアクセス制限が可能か | 運営中の問い合わせやトラブル対応は充実しているか |
| データ改ざん防止の対策が可能か | 法改正対応やシステムアップデートが迅速か |
どこまでサポートが受けられるのか、その際に費用はかかるのかなど、事前にしっかり確認しておきましょう。
無料トライアルのサービスはあるか
製品によっては本格導入前のトライアル期間が設定されているものもあるので、実際の活用をイメージしてトライアルやデモ機能をお試しすることがおすすめです。
システムを本格的に導入する前に、その使い勝手などはやはり事前に確認しておきたいもの。いくつか製品をピックアップした上で、「無料トライアルが可能か」「トライアルは有料なのか無料なのか」「どこまでの機能が試せるか」「トライアル期間はどのくらいの長さなのか」など、サービス提供会社に問い合わせてみるとよいでしょう。
導入コスト、運用コストが自社に見合っているか
勤怠管理システムの導入に際しては、自社の企業規模や業務状況に費用対効果が見合っているかどうかを見極めておくことも大切です。
タイムカードの場合は、少なくとも毎月の運用費はかかりません。しかし、勤怠管理システムは導入する際のコストに加え、毎月の運用やシステム改修に際してもコストがかかってくるのが一般的です。導入すれば非常に便利ではあるものの、従業員数や業態によっては旧来のタイムカード方式による勤怠管理で十分といったケースもあり得ます。
たとえば、従業員規模が数名程度の企業では勤怠管理の手間が比較的少ない場合が多いため、あえてコストをかけてでもシステム導入すべきなのかは見極めが必要です。
現状の勤怠管理にかかっている時間や人件費を明確にした上で、勤怠管理システムの導入や運用にかかるコストが自社に見合っているのか確認しておきましょう。
中小企業向けの勤怠管理システムに関してよくある質問
中小企業の勤怠管理システム選定については、大企業とは異なる中小企業の特性に合ったシステムを選ぶことが導入成功への第一歩です。
ここでは中小企業ならではの目線で、勤怠管理システムの導入についてよくある質問をまとめています。
中小企業の定義とは?
中小企業庁の定義によると、中小企業の定義は、業種・資本金または出資総額・常時使用する従業員の数により以下のように分かれています。
| 業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
| 製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
| 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
| 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
| サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
従業員が少ない場合、勤怠管理は手動での計算で何とか対応できるケースがあるかもしれません。一方、中小企業においては雇用形態もさまざまです。
シフトが複雑な従業員がいるようなケースでは、小規模でありながらも勤怠管理が複雑になっている特徴があり、その場合は勤怠管理システムの導入にメリットがあります。
中小企業向けと大企業向けのシステムの違いとは?
中小企業の担当者が勤怠管理システムを導入する際には、大企業の勤怠管理とは違った目線での検討が必要となります。
中小企業は従業員の規模感が大企業よりも小さいため、「基本的な機能が充実しているか」「規模に応じた少人数の契約でも対応可能か」といった点がシステム選定のポイントとなります。
| 中小企業向け | 大企業向け |
| 基本的な勤怠管理機能が充実しているか | 独自のルールに即した機能のアレンジが可能か |
| 小人数に応じた料金設定があるか | 大人数でも問題なく処理できるか |
| 導入・運用のコストや工数が手軽か | 複数の管理者・拠点で導入可能か |
設定に時間をかけられないが初めての導入でも大丈夫?
初期設定の立ち上げにあまり工数がかけられないようなときは、導入の際のサポート体制が充実しているかをチェックするとよいでしょう。
製品よっては初期設定の代行をしてくれるサービスや、導入後に専任担当者が伴走してくれるサポート体制が整っているケースもあります。
サポ―ト方法はメールや電話などシステムによって異なりますが、初めて勤怠管理システムを利用する際には、操作しながらリアルタイムでサポートしてもらえる電話やオンラインサポートを選べるとよいでしょう。
製品が多すぎてどれを選べばよいのか迷った場合の選定時のコツは?
いきなりひとつの製品を選ぼうとせず、まずは複数のサービス提供会社に問い合わせをして相談することをおすすめします。その後、数社トライアルしてみて、自社にぴったりのサービスを見つけるようにしましょう。
いろいろなシステムを比較することで、自社に必要な項目を取捨選択できるようになります。すでに自社で勤怠管理システムを導入しており、システムの切り替えを検討している中小企業であれば、現サービスの課題と、今後どんなことを実現していきたいのかを明確にすることで、新たなシステムをスムーズに選ぶことができるのではないでしょうか。
中小企業の勤怠管理にはクラウド型システムの「楽楽勤怠」がおすすめ
中小企業の従業員の勤怠管理には、大企業とは異なるさまざまな課題があります。その課題解決には、クラウド型の勤怠管理システムの導入がおすすめです。
株式会社ラクスが提供するクラウド型勤怠管理システム「楽楽勤怠」は、従業員の日々の労働時間や時間外労働時間、休暇取得などの状況をリアルタイムで一元管理できるので、入力漏れや集計ミスを防ぎ、ひいては賃金の未払いなどの労務リスクの発生防止にも役立ちます。また、法改正に対しては自動アップデート機能により速やかな対応が可能です。
一方、すでに勤怠管理システムを導入している企業でも、一部Excelなどの手計算が発生していたり、「自社の従業員の働き方にマッチしていない」「使いこなせてない」「コストがかかっている…」などの悩みがあるかもしれません。中小企業だからこそ、個々の従業員に沿ったきめ細やかな設定・管理ができるシステムの導入が求められています。
勤怠管理システムは導入して終わりではありません。長く使うからこそ、充実したサポート体制があれば安心です。クラウド型勤怠管理システムの「楽楽勤怠」には、中小企業における勤怠管理の悩みを解決する機能が多く備わっています。現状の勤怠管理に課題を感じている場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
メールで受け取る

働き方改革関連法へ対応!勤怠管理システム「楽楽勤怠」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
- 監修楽楽勤怠コラム編集部
- 「楽楽勤怠」コラム編集部です。
人事労務担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報をお届けしています。
https://www.rakurakukintai.jp/
こんなお悩みありませんか?
そのお悩み で解決できます!
で解決できます!

実際のシステム画面をお見せしながら
現在の運用方法についてお伺いし、
貴社に合わせた運用提案を
させていただきます。
ご要望に合わせてWEBでのご案内も可能です。
知りたい方はこちら

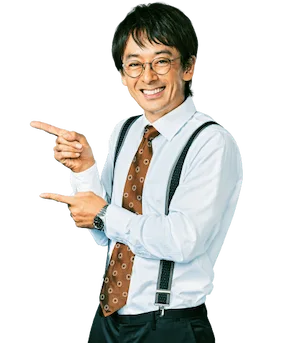
 とは
とは
「楽楽勤怠」は勤怠管理・給与計算を
ラクにするクラウド型のシステムです。
- 従業員
- 従業員ごとに用意されたアカウントにログインし、打刻や勤怠申請を行います。
- 「楽楽勤怠」
- 勤怠情報をシステムで一元管理し、給与計算に必要なデータを自動集計します。
- 人事労務担当者
- システムからデータ出力して給与システムに連携するだけで簡単に給与計算を行うことができます。
出退勤や残業、休暇取得などの勤怠情報を一元管理し、給与計算に必要なデータを1クリックで出力します。
インターネットに接続可能なパソコンやスマートフォンがあれば外出時や在宅ワーク時にも利用可能です。
あなたの会社の働き方改革に貢献する勤怠管理システムです。
「楽楽勤怠」が
選ばれている理由

豊富な機能群
現状運用にあわせた課題解決や業務効率化を実現します。

初めても乗り換えも安心の、
専任サポート
※2024年3月末現在
ご要望に合わせてWEBでのご案内も可能です。
知りたい方はこちら

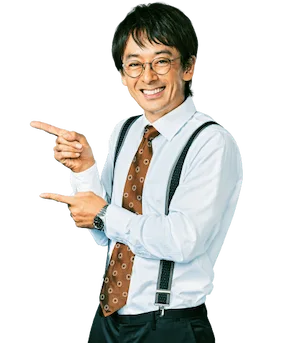
関連サービスのご紹介
「楽楽勤怠」の姉妹製品・関連サービスのご紹介です。
バックオフィス業務のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ83,000社以上のご契約をいただいています(※2024年3月末現在)。「楽楽勤怠」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。
「楽楽勤怠 クラウドサービス」は「IT導入補助金2024」の対象ツール(通常枠のみ)です。
補助金を受けるためには、導入契約を締結する前にIT導入補助金事務局(事務局URL:https://it-shien.smrj.go.jp/)に対して交付申請を行う必要がありますので、その点に留意してください。
なお、補助金の交付を受けるには所定の要件を満たす必要があります。
※現在は申請期間外となります。


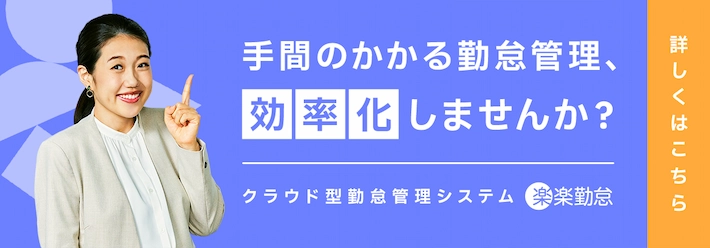
 とは
とは




