業務の効率化に寄与する工数管理とは?実施の手順と管理ツールの選択

工数管理とは、プロジェクトや業務における作業時間や労力(=工数)を計画・記録・分析し、適切に管理することを指します。
作業に要する時間や負担を可視化し、無駄を削減することで、業務の効率化と生産性向上が期待できます。さらに、工数管理に勤怠データを組み合わせることで、「時間」と「業務内容」の両面から従業員の働き方を把握することが可能です。加えて、働き方の可視化が進めばより適切な人員配置の実現につながり、労務リスクの低減にも寄与します。
しかし、どのようなツールが自社に最適なのかや、導入方法・運用のやり方などわからない点が多いかもしれません。
この記事では、工数管理の基礎知識や管理ツールを選ぶ際のポイント、導入時の注意点などについて詳しく解説していきます。
この記事の目次
工数管理とは何か?
工数とは、ある作業を完遂するために必要な作業量のことです。「作業時間×人数」で算出した工数の記録・分析を行い、可視化して管理することを「工数管理」といいます。
管理の単位は、一人の作業員が1か月で行った作業量を表す「人月(にんげつ)」を用いるのが一般的です。作業ごとに「人月」を算出することで、どの作業に対してどの程度のコストがかかっているのかを明確にできます。
工数管理で作業ごとのコストを把握できれば、無駄なコスト削減につながるだけでなく臨機応変な作業員の配置転換も可能になり、トータル的な業務効率化および改善につながるでしょう。
以下では、工数管理の目的と勤怠管理との違いについても解説します。
工数管理の目的
工数管理の目的は、自社の利益率の正確な把握と各プロジェクトの成功率を高めることです。
工数が正確に把握できていないと、一見好成績に見えていても、実際は予想よりも利益が少ないというケースも珍しくありません。
適切なリソース配分やスケジュール管理のために、「どの業務に」「誰が」「どの程度時間がかかっているか」といったプロジェクトの進捗状況を可視化します。工数管理を徹底すれば、無駄なコストの改善だけでなく生産性の合理化を図ることが可能です。
また、経営者および労務担当者にとっては、工数管理で集計したデータをもとに必要に応じた対策を迅速に行うことができるため、自社の利益率の向上につながるでしょう。
工数管理と勤怠管理の違い
工数管理と勤怠管理の違いの前に、工数と労働時間の違いについて以下の表を参考に整理しておきましょう。
| 工数 | 労働時間 |
| 特定のプロジェクトや業務に実際に費やした時間 | 自社の就業規則で定めた労働時間 |
工数管理がプロジェクトを管理することで業務効率化を図るのに対し、勤怠管理は従業員の労働時間を記録・管理することでコンプライアンス遵守につなげるのが目的です。また、工数管理は法的義務がありませんが、勤怠管理については2019年4月改正の労働安全衛生法により「企業は従業員の正確な勤怠情報を把握する義務がある」とされ、客観的な記録による勤怠管理が義務付けられたことが特徴といえます。
このように、工数管理と勤怠管理には大きな違いがありますが、企業の成長や業務効率化に欠かせないことが共通点です。
※(参考)「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずるべき措置に関するガイドライン」
工数管理を実施するメリット3選
工数管理を行うメリットはいくつかありますが、業務改善はもちろんのこと、社内組織の活性化につながることが共通点です。
工数管理を実施することで、特に得られるメリット3つをご紹介します。
①プロジェクト単位の進捗状況をリアルタイムで管理できる
工数管理によってプロジェクトに関する情報を一元化すれば、支社や支店での進捗状況もリアルタイムに管理できます。
各地に支社や支店を置いている企業は多いものですが、一つのプロジェクトを全社的に進めているような場合、各地で個別に管理するのは非効率です。なおかつ各地の担当者にも過度な負担がかかり、プロジェクト自体の遅延といったトラブルにもつながりかねません。
しかし工数管理を実施すれば進行がスムーズになり、プロジェクト自体の精度を高めることも期待できるでしょう。
②成果が可視化され生産性の向上につながる
工数管理を行うと、「誰がどの程度の作業量を抱えているのか」を可視化することができます。
作業スキルに偏りがある場合には人員配置の変更など適切な対応を行い、常にプロジェクト体制を最適化できることは大きなメリットです。また、従業員にとっては成果が可視化されることで、具体的な業務効率化の方法をイメージしやすくなります。
工数管理を適切に行うことにより、社員のモチベーションアップはもちろん、生産性の向上にもつながってきます。
③コスト意識が高まり利益率の改善を目指せる
工数管理によってタスクを可視化すれば、無駄な作業を特定することができるため、作業プロセスなどの見直しで人件費を中心としたコストの削減が期待できます。
どの部分を改善すればよいのかが明確になるので、現在のプロジェクトだけでなく、次回以降のプロジェクトにも蓄積した経験を反映させることが可能です。
コスト意識が担当者だけでなく現場でも高まり、具体的な行動の積み重ねによって利益率の改善を目指せることが工数管理を行うメリットといえるでしょう。
工数管理の手順
工数管理を行っていく場合、工数管理全体をマネジメントする担当者は、その手順を理解していなければなりません。
ここでは工数管理を行う手順と、それぞれの流れの中でのポイントについて紹介します。
工数を見積もり工程表を作成する
担当者を決めて工数管理の意義を周知させた後は、実際に工程表を作成していきましょう。
工程表の作成に必要な工数を見積もるには、プロジェクトの対応範囲や目標設定を行い、それに向けたタスクの洗い出しが欠かせません。このときに大切なのは、無理のないスケジュールによる工程表の作成です。余裕を持ったスケジュールを組まないと、進捗状況の把握が難しくなったり、担当者に過度な負担が生じたりします。ひいては職場の雰囲気が悪くなり、社員のモチベーション低下につながりかねません。
個々の社員の能力や作業スピードなど、実情を正確に反映した工程表を作成することが、スムーズなプロジェクト進行を行ううえで重要です。
事前の見積もりと実績を比較する
事前の見積もりを反映した工程表を作成し、工数管理を行う準備ができたら実践に移ります。
工数入力は、Excelや工数管理ツールを利用するのが一般的です。精度の高い工数管理を行うため、毎日の工数入力はできるだけ詳細に入力するよう、担当者は周知徹底に努めてください。また、担当者は入力チェックだけでなく、事前の見積もりに対して計画通りに進んでいるかどうかを確認することが重要です。
さらに、日々蓄積されていくデータは担当者だけが確認するのではなく、全体で共有できる体制を整えておくことも大切なポイントといえるでしょう。
比較情報を分析し改善を図る
継続的に工数管理を行うことで、定期的に事前の見積もりと比較して分析しましょう。データ分析を進めることで、当初の予定よりコストがかかっている部分、あるいは想像以上に利益が出ているプロジェクトなど、優れている点と改善しなければならない点が明確になります。
また、データ分析はプロジェクト単位だけでなく、チーム単位など多角的に行うことが、柔軟なスケジュール修正のみならず、次回のプロジェクト運用に引き継ぐためにも重要です。
プロジェクト終了時には全体を振り返り、よかった点・悪かった点を明確にし、関係者各位へ速やかに報告しましょう。
工数管理の注意点4つ
適切な工数管理の運用が企業にさまざまなメリットをもたらすことは、これまで見てきた通りです。一方、工数管理を行ううえで事前に覚えておいた方がよい注意点がいくつかあります。
それぞれの具体的な内容を見ていきましょう。
①管理の目的と範囲を明確にする
工数管理の重要性やメリットを従業員に理解してもらうには、その目的を明確にしておくことが大切です。
工数管理の主な目的は、企業側においてはプロジェクトの収支把握によるコスト削減、現場サイドとしては進捗状況の把握による業務効率化などです。適切な工数管理を実現するには従業員の協力が必要なため、こうした目的をわかりやすく説明しておくとよいでしょう。ただ、あれもこれもと工数管理を行う範囲を広げすぎると、管理そのものが煩雑になってしまいます。
目的と範囲が不明瞭なまま工数管理に取り組んでしまうと、プロジェクト全体の精度が低下する可能性も出てくるので注意しましょう。
②正確なデータを記録する
正確な作業時間の記録は、工数管理をスムーズに進めるうえで大切です。
企業によっては、複数のプロジェクトを同時に管理している場合や、担当者が遠隔地に配属されているケースもあるでしょう。入力忘れなど不正確なデータ収集が続くと、プロジェクトの正確な進捗状況の把握が難しくなり、規模が大きければ大きいほど担当者にかかる負担も膨大になってしまいます。こうした状況では工数管理全体の信頼性が損なわれてしまい、社内のモチベーション低下にもつながりかねません。
「タスクを終えるたびに担当者が記録する」「業務終了時に責任者が1日分をまとめて記録する」といったように、誰がいつ入力するか決めておくなどの対策を講じて、正確なデータ入力の徹底に努めましょう。
③細かすぎる管理は避ける
正確なデータが必要だからといって、細かすぎる工数管理とならないように気を付けましょう。
細かすぎる入力や無理なスケジュールでの作業は従業員のモチベーション低下を招き、生産性が下がるリスクがあります。また、工数管理自体に時間をかけすぎてしまい、実作業が遅れてしまっては本末転倒です。
工程表を作成する際には、予期せぬ遅延が生まれる状況も考慮した、余裕のあるスケジュールを組むよう留意しながら取り組みましょう。
④コミュニケーションを密に行う
工数管理において、コミュニケーションを密に行うことは非常に重要だといえます。
工数管理の本来の目的は、業務の効率化や改善です。そのため、単に数字を追うだけでなく、プロジェクトを成功に導くためにチーム全体で協力して取り組むことが大切だといえます。
メンバーごとの工数や進捗、正確な情報の共有などを密に行うことを意識して工数管理に取り組みましょう。
工数管理の主な方法2選
工数管理を行う方法は、大きく分けて「Excelを活用する方法」と「工数管理ツールを導入する方法」の2種類があります。
ここでは、それぞれのメリットやデメリットを解説していきます。導入を検討する際の参考にしてください。
①Excelなどの表計算ソフトを使用する
Excelを利用するやり方は、比較的簡単に行える工数管理方法といえます。
具体的な流れは、以下の通りです。
- 工数管理に必要な基本項目を決める
- テンプレートを作成する
- 計算や分析のためのシート設定を行う
- 作業進捗に応じて進捗や実績を更新する
- データを収集して分析する
Excelを使用した工数管理は、コストが抑えられる・使い慣れている人が多いなど、手軽に取り入れやすい点がメリットです。一方で多角的なデータ分析を行う場合は機能に限界があるため、あまり複雑な管理には適していません。管理するプロジェクトが増えるほどファイル管理に手間がかかる点や、データサイズが大きくなると更新や編集に時間がかかる点はデメリットだといえます。
そのほか、リアルタイムでのデータ更新やカスタマイズが難しいことからも、中長期的な運用やプロジェクトでは専用の工数管理ツールの検討がおすすめです。
②専用ツールを使用する
工数管理に特化したツールの場合、工数管理を行うためのさまざまな機能が搭載されています。そのため、Excelでは限界のある複雑な操作ができることが大きなメリットです。また、複数のプロジェクト管理をスムーズに行える点や入力エラーを防ぎやすい点も工数管理ツールの特徴といえます。
工数管理ツールには、工数管理機能のみのツールだけでなく勤怠管理システムに工数管理機能が含まれているものもあるなどさまざまな種類があり、自社に合った機能に特化したツールを選ぶことが可能です。工数管理を組み込んでいる勤怠管理システムを導入すれば、データを一元化して管理できるのも、工数管理ツール導入を検討する際に押さえておいたほうがよいポイントでしょう。
一方、工数管理ツールの導入にはコストがかかります。また、従業員がツールに慣れるまでの時間も計算に入れておいたほうがよいでしょう。
とはいえツール活用により結果的に工数管理にかかる人件費や作業時間を大幅に削減できる場合もあるため、自社の状況や従業員のスキルをよく鑑みて、どちらがよりよい工数管理を実現できるのか検討してください。
工数管理は勤怠管理システムでの一元化がおすすめな理由4選
工数管理を行うことは企業にとってさまざまなメリットがあります。
しかし、企業の規模によってはデータの共有が難しかったり、入力や集計の手間がかかったりする場合もあるでしょう。また、正確なデータを記録しても、活用しきれないなどのケースも考えられます。
その点、工数管理機能を搭載した勤怠管理システムを導入すれば、工数管理データと勤怠管理データを掛け合わせることでデータの整合性が高まるほか、さらなる業務効率化を目指すことが可能です。
その理由について、以下で確認していきましょう。
①入力・集計の負担が軽減できる
工数管理機能付きの勤怠管理システムを活用すれば、工数の入力や集計にかかる負担を大幅に削減できます。
Excelなどを用いた手作業での工数入力は、ミスが発生しやすく、チェック作業も担当者にとって大きな負担となりがちです。しかし、勤怠管理システムに工数管理機能を備えれば、入力ミスを防ぎつつ、集計の手間も削減できます。さらに、勤怠データと突合してプロジェクトと実労働時間との差分を自動でチェックできるため、それぞれのデータを手作業で照らし合わせて過少・過大申告がないかを確認する手間は不要です。
工数と勤怠を一元管理できることは、システム導入の大きなメリットといえるでしょう。
②データの共有や更新をリアルタイムで行える
工数管理が行える勤怠管理システムを導入すれば、実労働時間と連動した工数情報をリアルタイムで容易に把握することができるため、経営者や担当者が状況判断を迅速かつ的確に行うことができます。
高度な情報化社会において、情報のスピードと精度は業務効率化に欠かせない要素です。また担当者にとっては、給与計算やコスト計算の正確さが向上する点も、手作業で行う工数管理と比較した場合の大切なメリットでしょう。
③データをもとにした適切な人員配置ができる
工数管理機能を備えた勤怠管理システムは、工数データと勤怠データを一元管理できるため、整合性のとれたデータを基にした適切な人員配置が目指せます。
それぞれのプロジェクトで従業員が取り組んでいる仕事量はもちろん、労働時間も正確なデータとして可視化されます。手作業とは異なり集計も自動で行えるため、事前の見積もりと実労働時間の差分チェックが可能です。
仮に予想外の出来事によって急な応援などが必要な場合でも、正確なデータをもとに適切な人員配置を行えることは、業務の効率化はもちろん適材適所の人員配置につながります。
④労務リスクの削減につながる
勤怠管理システムのメリットのひとつは、労務リスクにつながりかねない、従業員の長時間労働などの状況を随時チェックしながら改善しやすい部分です。
ほとんどの勤怠管理システムは、パソコンやタブレット、スマートフォンなどの豊富な打刻手段を備えています。つまり、工数管理機能付きの勤怠管理システムであれば、工数の入力手段も豊富ということです。出張時や在宅勤務などを含め、時間や場所を問わず入力できるのも、工数管理のみの専用ツールとは大きく異なるポイントといえます。
工数管理における正確なデータの収集によって、人事労務担当者は従業員の長時間労働をはじめとする労務リスクを早期に発見・改善することが可能です。また、従業員にとっては正確なデータをもとに自分の仕事に集中できるので、生産性向上の効果が見込めるでしょう。
工数管理ツールの選定ポイント3点
工数管理ツールを導入することが、手作業の工数管理に比べてメリットが多いことはご理解いただけたかと思います。
しかし、工数管理ツールとひと口にいっても、製品によって特徴はさまざまです。何を基準に選べばよいのかはっきりしないと悩む担当者も多いのではないでしょうか。
そこで、ここからは自社に適した工数管理ツールを選ぶためのポイントについて解説していきます。
①自社業務、プロジェクトに適合するか
工数管理ツールを選ぶ際には、自社の業務やプロジェクトにマッチするのかを確認しておきましょう。
ついつい機能が豊富な製品に目が行きがちですが、大切なことは、機能の豊富さだけでなく自社の目的を達成するための機能が備わっているかどうかです。いくら機能が豊富でも、必要でない機能が多かったり使いこなすのが難しい機能が多かったりすると、かえって業務の煩雑化を招いてしまって本末転倒です。
自社業務およびプロジェクトにそれぞれの機能が適しているかどうかを基準に、どのツールを導入するかを検討するようにしましょう。
②入力を容易に行えるか
工数の入力がスムーズに行えるかも、ツール選定の際に重視したいポイントでしょう。
工数管理ツールは担当者だけでなく、全メンバーが日常的に使用するツールです。したがって、誰でも使いこなせるような操作性を重視する必要があります。
とりわけ入力しやすいかどうかは大切なポイントで、いくら機能が豊富であっても習得までに時間や手間がかかるツールを選んでしまうと、逆に業務効率が低下してしまうので注意しましょう。
③工数情報の分析が可能か
工数情報の分析が可能かどうかは、工数管理で得たデータを有効活用するために必須の機能なので、事前にチェックしておきましょう。
工数管理ツールは、工数実績などさまざまな情報を可視化してくれます。しかし、すべてのツールに同じ機能が搭載されているとは限りません。
ほかの機能が充実していても、工数情報の分析機能の有無を忘れることなくチェックするようにしましょう。
工数管理ツール導入の流れ
工数管理ツールの導入には、大きく分けて以下のように5つのステップがあります。
- 業務フローの明確化
- ツール選定
- 導入計画立案
- トライアル
- 全社導入
自社に適した工数管理ツールを選ぶために、まず担当者が中心となって現状分析を綿密に行いましょう。工数管理ツールを導入することで、自社の何を効率化および改善したいのかを明確にすることは極めて大切です。また、導入に向けては全社にその意義を徹底する必要があり、その際にはできるだけ具体的かつわかりやすい表現に努めるようにしましょう。
次に、業務フローの明確化にもとづいてツールを選定する際は、複数のツールを比較検討することが大切です。ツールによっては業種に特化した製品もあるので、自社の特徴も踏まえてよく吟味しましょう。
自社に合ったツールを選定した後は、導入計画の立案です。余裕を持ったスケジュールを心がけ、「トライアル」を行う中で現場とのコミュニケーションを密にし、ツールの使用方法や運用方法などを周知徹底させていきましょう。
そして、工数管理ツールの全社導入という流れになります。ただし、工数管理ツールは導入すれば終わりというものではなく、むしろ導入してからが本番といえます。
導入後の運用をスムーズに継続させていくためにも、一つひとつのステップを焦ることなく、着実に遂行していきましょう。
クラウド型システム「楽楽勤怠」で勤怠管理と工数管理を一元化しよう
本記事では企業の業務効率化に寄与する工数管理の基礎知識やメリット、ツールの選定方法などについて解説してきました。
特に、工数管理機能付きの勤怠管理ツールを導入することによりデータ活用がより有効になる点やコスト削減が容易にできるという点は、業務効率化を図りたい担当者にとって大きなメリットではないでしょうか。
株式会社ラクスが提供しているクラウド型勤怠管理システム「楽楽勤怠」は、オプションとして「工数管理機能」を追加することが可能です。
工数管理と勤怠管理の一元化により、さらなる業務効率化と担当者および従業員の負担軽減が実現します。ぜひ一度ご検討ください。
メールで受け取る

働き方改革関連法へ対応!勤怠管理システム「楽楽勤怠」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
- 監修楽楽勤怠コラム編集部
- 「楽楽勤怠」コラム編集部です。
人事労務担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報をお届けしています。
https://www.rakurakukintai.jp/
こんなお悩みありませんか?
そのお悩み で解決できます!
で解決できます!

実際のシステム画面をお見せしながら
現在の運用方法についてお伺いし、
貴社に合わせた運用提案を
させていただきます。
ご要望に合わせてWEBでのご案内も可能です。
知りたい方はこちら

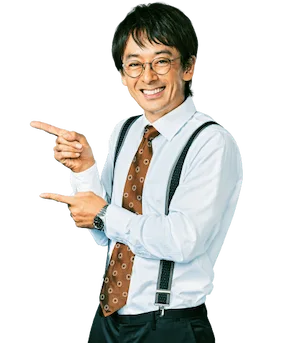
 とは
とは
「楽楽勤怠」は勤怠管理・給与計算を
ラクにするクラウド型のシステムです。
- 従業員
- 従業員ごとに用意されたアカウントにログインし、打刻や勤怠申請を行います。
- 「楽楽勤怠」
- 勤怠情報をシステムで一元管理し、給与計算に必要なデータを自動集計します。
- 人事労務担当者
- システムからデータ出力して給与システムに連携するだけで簡単に給与計算を行うことができます。
出退勤や残業、休暇取得などの勤怠情報を一元管理し、給与計算に必要なデータを1クリックで出力します。
インターネットに接続可能なパソコンやスマートフォンがあれば外出時や在宅ワーク時にも利用可能です。
あなたの会社の働き方改革に貢献する勤怠管理システムです。
「楽楽勤怠」が
選ばれている理由

豊富な機能群
現状運用にあわせた課題解決や業務効率化を実現します。

初めても乗り換えも安心の、
専任サポート
※2024年3月末現在
ご要望に合わせてWEBでのご案内も可能です。
知りたい方はこちら

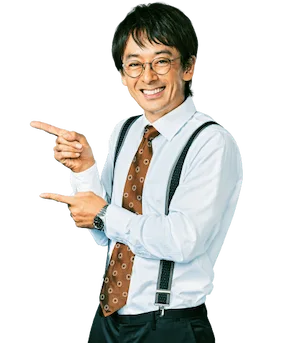
関連サービスのご紹介
「楽楽勤怠」の姉妹製品・関連サービスのご紹介です。
バックオフィス業務のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ83,000社以上のご契約をいただいています(※2024年3月末現在)。「楽楽勤怠」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。
「楽楽勤怠 クラウドサービス」は「IT導入補助金2024」の対象ツール(通常枠のみ)です。
補助金を受けるためには、導入契約を締結する前にIT導入補助金事務局(事務局URL:https://it-shien.smrj.go.jp/)に対して交付申請を行う必要がありますので、その点に留意してください。
なお、補助金の交付を受けるには所定の要件を満たす必要があります。
※現在は申請期間外となります。


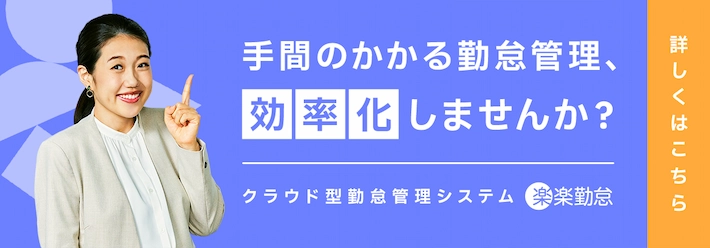
 とは
とは




